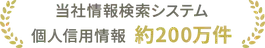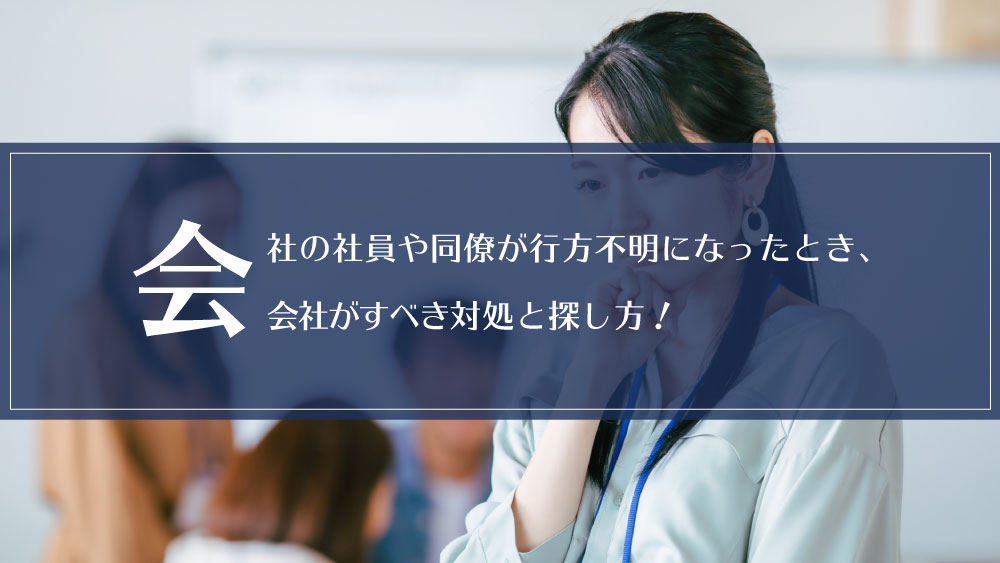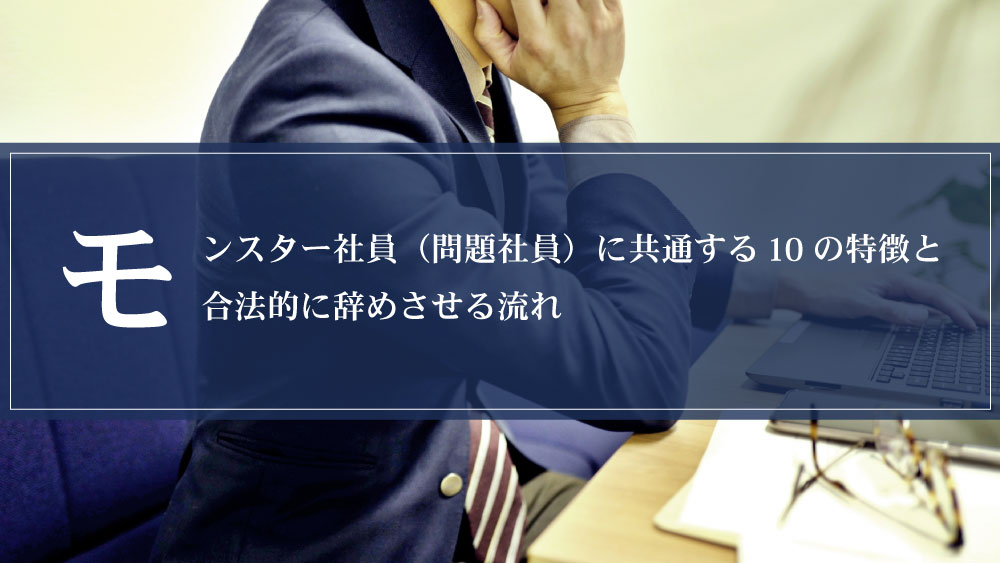サッと読める!
ためになるSATコラム
カテゴリーで絞り込み
個人向け調査
セクハラ・パワハラを訴える!違法性と法的責任、証拠収集に探偵の調査
【投稿日】2018年6月5日

セクシュアル・ハラスメント(通称セクハラ)やパワーハラスメント(通称パワハラ)は、被害者自身が受ける心身の傷やストレスだけでなく、職場環境や企業風土の悪化を招くため、予防や対策に取り組む企業は増加傾向にあります。ところが、セクハラやパワハラの相談件数は依然として高い水準を推移しているのが原状です。
そこで今回は、セクハラやパワハラの被害者の方向けに、セクハラ・パワハラの基礎知識から対処方法、被害を訴える際に必要不可欠な証拠について徹底解説します。
また、告訴や提訴を検討している場合は、被害を立証する上で是非利用したい探偵事務所のセクハラ・パワハラ調査についても、詳しくご紹介します。
セクハラ・パワハラとは

セクハラ・パワハラ被害に適切に対処できるようになるためにも、まずはセクハラとパワハラについて知っておく必要があります。
ここでは、セクハラ・パワハラの定義や分類、さらにはこれらの嫌がらせが企業にとってどのような損失を与えるかを解説します。
セクハラの定義と分類
セクハラとは、職場で性的な嫌がらせをする行為です。相手の身体に直接触れる性的嫌がらせと、性的な発言による嫌がらせとがありますが、「改正男女雇用機会均等法」では、セクハラを「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」に分けて捉えています。
「対価型セクハラ」とは
「対価型セクハラ」とは、社内の地位や役職を利用して、相手に性的な要求を行うタイプのセクハラです。相手が要求を拒否した場合は、社内の立場や上下関係を利用して解雇・降格・減給などの不利益を相手に与えます。
- 上司が異性の部下に対して、待遇アップを条件に交際や性交渉を要求する。
- 男性上司が部下の女性社員に交際を申し込んで拒否された結果、女性社員は正当な理由なく減給処分を言い渡された。
「環境型セクハラ」とは
セクハラ行為によって職場環境を悪化にさせるのが、「環境型セクハラ」です。社員が看過できないほどに業務上の支障をきたします。「環境型セクハラ」はさらに「視覚型」「発言型」「身体接触型」に細かく分類することができます。
- パソコンのデスクトップ画像やスクリーンセーバーにわいせつな画像を用いる。
- 宴会で酔った勢いで全裸を晒す。
- 社内でわいせつな会話やジョークで盛り上がる。
- 女性社員の容姿や体型を過度に褒めたり、逆にけなしたりする。
- 労をねぎらうつもりで、女性社員の肩を揉む。
- 部長室に女性社員を呼び出して、身体に触ったり性交渉を迫ったりする。
パワハラの定義と分類
パワハラとは、役職・肩書きなどの地位や、職場内の人間関係における優位性を利用して、虐めや嫌がらせを行う行為です。中でも、業務上で必要な注意・指導・命令などの適正範囲を超えた行為がパワハラと見なされます。
また厚生労働省では、過去の裁判例や労働紛争の個別事案に基づき、パワハラを以下の6種類に分類しています。
- 身体的な攻撃(暴行・傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
- 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外れにする・無視)
- 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制や、仕事の妨害)
- 過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
※出典: 厚生労働省ホームページ>政策について>分野別の政策一覧>雇用・労働>雇用均等>職場のパワーハラスメントについて
セクハラ・パワハラがもたらす企業リスクとは
社内でセクハラやパワハラが日常的に発生していたり、嫌がらせが常態化していたりする企業は、様々なリスクを抱えています。企業全体としてはもちろん、社員一人ひとりがこれらのリスクを理解した上で、意識改革やセクハラやパワハラの予防・対策に取り組む必要があります。
職場環境の悪化による人材流出
セクハラやパワハラが常態化もしくは悪化することで、職場環境の悪化を招き、社員のモチベーションの低下に繋がります。社員のやる気が低迷すれば、優秀な人材は働きやすい職場を求め、人材の流出に歯止めがかからなくなる恐れがあります。
企業モラルの低下・悪化
企業モラルは、個々の社員の倫理観や善悪の判断基準が、企業風土や社風として反映されたものです。セクハラ・パワハラが常態化したり、これらの嫌がらせを黙認したりしている職場では、企業モラルの悪化にも繋がりかねません。
企業イメージの悪化
セクハラ・パワハラ行為が公になることで企業イメージが損なわれるのは必至です。会社のブランドイメージや社会的信用も失われることで、売上の損失などにも繋がります。
直接的損失
セクハラやパワハラを受けた社員によって損害賠償請求や刑事告訴された場合、弁護士費用や裁判費用、裁判にかかる時間などの直接的損失も被ります。
セクハラ・パワハラ行為の違法性について考える
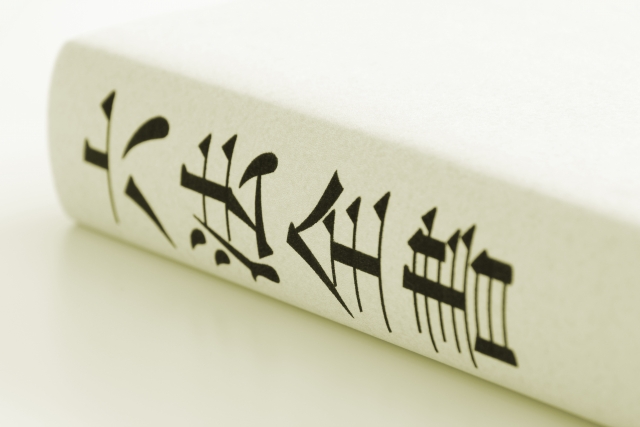
セクハラやパワハラはなぜ違法なのでしょうか。ここからは、セクハラ・パワハラがただの虐めや嫌がらせにとどまらず、違法行為として刑事告訴や民事訴訟も可能である法的根拠について、詳しく解説します。
セクハラ行為が違法と見なされる法的根拠
セクハラが違法であると判断される最大の根拠となる法律は、日本国憲法の「基本的人権」や「個人の尊重」です。セクハラはこれらの権利を侵害する行為であるため、「改正男女雇用機会均等法 第11条」では、企業に対してセクハラの予防・対策を義務づけています。
日本国憲法
セクハラ行為の違法性を考える際に重要な鍵となるのは、日本国憲法の「基本的人権(第11条)」と「個人の尊重(第13条)」です。基本的人権は憲法によって保障されており、何人もこれを侵害することはできません。また、国民一人ひとりの個人としての権利や尊厳は、最大限尊重されます。
改正男女雇用機会均等法
憲法で保障された「基本的人権」と「個人の尊重」に基づき、「改正男女雇用機会均等法 第11条」では、職場内でのセクハラ行為の予防・対策義務を企業に課しています。
第十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
企業は、社内での性的嫌がらせによって特定の社員が不利益を受けないよう、また、職場環境が悪化しないよう、セクハラ行為に適切に対応する義務を負っているのです。
具体的には、以下に挙げる対策を行わなければなりません。
- 相談しやすい環境や体制の整備
- 予防やセクハラ被害が発生した場合は、必要な対策の実施
- その他に雇用を管理するうえで必要な措置
セクハラが違法と見なされる条件(判例より)
セクハラ行為の違法性を判断する基準は、「金沢セクハラ事件」(名古屋高裁金沢支部判決平成8年10月30日労判707号)での判決文において言及されており、以下の条件を満たす場合、違法行為と見なされます。
- 加害者・被害者両者の役職・地位・上下関係
- 行為の場所・時間・内容や様子
- 被害者の対応
以上を考慮したうえで、行為が社会一般的に許容されるものではなく、行為の度合いが過剰と判断された場合。
パワハラ行為が違法と見なされる法的根拠
セクハラと同様、パワハラも「基本的人権」や「個人の尊重」を侵害する行為です。憲法で保障された権利や尊厳をもとに、「労働契約法(第5条)」では、企業に対して「労働者の安全への配慮」を義務づけています。
日本国憲法
セクハラと同様に、パワハラ行為が「基本的人権(第11条)」および「個人の尊重(第13条)」の侵害に当たるか否かが、パワハラの違法性を判断する上で最大の鍵となります。
労働契約法
「労働契約法」は労働者の保護や、企業と社員の労働関係の安定化を目的として制定された法律です。同法第5条に基づき、企業は社員の「生命・身体の安全や、プライバシーの保護、行動の自由など」を確保するために必要な配慮をするよう、義務づけられています。
セクハラ・パワハラ行為によって加害者や企業が問われる法的責任

職場のセクハラ・パワハラ行為は、加害者本人だけでなく、行為の内容や度合いによっては、加害者を雇用した会社も責任を追及されることがあります。
ここでは、セクハラとパワハラそれぞれによって加害者に生じる刑事責任と、セクハラ・パワハラの加害者本人や加害者の雇用主である会社が負うべき民事の損害賠償責任をご紹介します。
セクハラによって生じる刑事責任
セクハラの加害者が刑事告訴された場合、加害者は次に挙げる刑事責任を問われることがあります。
公然わいせつ(刑法第174条)
公共の場でのわいせつな行為をした場合。
→6ヶ月以下の懲役もしくは30円以下の罰金、または拘留もしくは科料(1,000円以上1万円未満の罰金)
強制わいせつ(刑法第176条)
13歳以上の男女に対して、暴行または脅迫によってわいせつな行為をした場合。
→6ヶ月以上10年以下の懲役
強姦(刑法第177条)
13歳以上の男女に対して、暴行または脅迫による姦淫(性行為)をした場合。
→3年以上の有期懲役
準強制わいせつ及び準強姦(刑法第178条)
相手を心神喪失状態に陥れたり、抵抗・拒絶できなくしたりして、わいせつな行為をした場合。
※「強制わいせつ罪」とは異なり、未遂も刑罰の対象。
→「強制わいせつ罪」と同様に6ヶ月以上10年以下の懲役
女性を心神喪失状態に陥れたり、抵抗・拒絶できなくしたりして、強姦した場合。
→3年以上の有期懲役
名誉毀(刑法第230条)
公共の場、もしくはインターネットやSNS上で相手の事実を暴いて名誉を毀損した場合。
→3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金
侮辱(刑法第231条)
事実を暴露せずとも、公然と相手を侮辱した場合。
→拘留または科料(1,000円以上1万円未満の罰金)
パワハラによって生じる刑事責任
パワハラの加害者が刑事告訴されると、セクハラと同様に以下の刑事責任を問われることがあります。集団での虐めや嫌がらせであると認められた場合は、パワハラに加担した人物全員に刑事責任が発生します。
名誉毀損(刑法第230条)
公共の場、もしくはインターネットやSNS上で相手の事実を暴いて名誉を毀損した場合。
→3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金
侮辱(刑法第231条)
事実を暴露せずとも、公然と相手を侮辱した場合。
→拘留または科料(1,000円以上1万円未満の罰金)
傷害(刑法204条)
他人に怪我をさせた場合。
→15年以下の懲役または50万円以下の罰金
暴行(刑法第208条)
相手に暴行を加えたものの、相手が怪我を負わなかった場合。
→2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料(1,000円以上1万円未満の罰金)
セクハラ・パワハラによって生じる民事責任
セクハラ・パワハラによる刑事責任は加害者本人に対して問われるものでしたが、民事責任の場合は加害者に限らず、雇用者である企業も責任を問われ、損害賠償を請求されることがあります。
・不法行為による損害賠償(民法第709条) ・財産以外の損害の賠償(民法第710条)
セクハラ・パワハラ行為を受けた場合、憲法で保護された「基本的人権」の侵害や、「労働者の安全配慮義務(労働契約法 第5条)」違反によって受けた不利益を理由に、セクハラ・パワハラの加害者に対して損害賠償を請求することができます。
なお、民法第709条では侵害された権利や利益に対する損害賠償責任について言及していますが、それを補足する形で同法第710条では、「財産以外の他人の身体、自由、名誉など」が侵害された場合についても、加害者に賠償責任が生じると明記しています。
使用者等の責任(民法第715条)
この規定によって、セクハラ・パワハラの加害者本人だけでなく、雇用者である企業や、加害者への指揮命令や監督を行う立場の人物に対しても、損害賠償を請求することができます。
なお、使用者責任の成立にあたっては、以下の条件を満たしている必要があります。
- 事業目的の使用関係がある
- 被用者(加害者と見なされる社員)が不法行為を行っている
- 上記の不法行為が職務の範囲内であると見なされる
- 免責事由がない
上記の免責事由とは、雇用主がセクハラ・パワハラの加害者である社員に対して相当な注意をした、あるいは相当な注意を行ったにもかかわらず損害が生じた場合を指します。
名誉毀損における原状回復(民法第723条)
民法での損害賠償は、同法第417条に基づき「金銭賠償」を原則としています(同法第722条)。この条文は「金銭賠償」の原則の例外を定めており、セクハラ・パワハラ行為によって被害者の名誉が毀損された場合は、裁判所は被害者からの請求によって「名誉を回復するのに適当な処分」を加害者に命じることが可能です。
セクハラ・パワハラを罰するその他の関連法
刑法・民法以外にも、セクハラやパワハラによって被害者が受けた不利益に対して、賠償を求めることを可能にする法律があります。会社法第350条「代表者の行為についての損害賠償責任」では、株式会社の形態をとっている企業に範囲を限定して、代表取締役が被害者に対して賠償責任を負うと定めています。
セクハラ・パワハラへの対処方法

セクハラやパワハラは、自身が被害者となってしまった時に具体的にどのように対処すれば良いのかわからず、一人で抱え込んでしまうケースが多いという実態があります。そのため、嫌がらせによるストレスなどから心身のバランスを崩してしまいがちです。
そこで、ここからは被害を受けた時に被害者自身が取るべき対応や、自身で対処しきれない、あるいは解決できない時に相談すべき第三者機関など、具体的な対処方法を詳しくご紹介します。
セクハラ被害に遭った時、被害者自身ができる対処方法
セクハラ被害に遭いかけたり、被害に遭ってしまったりした時は、身を守るために被害者自身ができる対処方法がいくつかあります。
- 加害者に対して、はっきりと拒否の意思を示す。
- 被害の詳細を記録する。(日時・場所・加害者氏名・加害者の言動など)
- セクハラ行為を録音・録画する。
- 加害者から受け取ったメール・手紙・プレゼントは処分せず、手元に残す。
- 現場に目撃者がいた場合は、目撃者の氏名や所属などをメモする。
- セクハラによるストレスから心身に不調をきたして医療機関にかかった場合は、医師に診断書を書いてもらう。
- 社内で相談できる人物を見つける。(信頼できる相手であることが条件)
- 社内のセクハラ相談窓口や労働組合へ相談する。
セクハラ行為をエスカレートさせないためには、初期の段階で相手にはっきりと「NO」と言うことが重要です。また、被害内容は第三者へ相談する際や、訴訟を起こす際の重要な証拠となりますので、詳細を記録しておきましょう。
社内でセクハラについて相談する際に気をつけたいのが、「人の口に戸は立てられぬ」と言うように、セクハラ行為が噂として広まってしまうことです。被害者が特定されてしまうと、被害者自らの社内での立場が悪化する可能性があります。
パワハラ被害に遭った時、被害者自身ができる対処方法
パワハラの被害に遭った際、被害者ができることはセクハラ行為を受けた時と基本的には同じです。
ただし、セクハラとは異なり、パワハラは「虐め」であるため、パワハラ行為を受けた時に即座に拒否することで、虐めや嫌がらせがエスカレートしかねません。被害者自らが対処するのが困難なケースが多いため、その場で明確な拒否・拒絶の意思は示さず、被害の記録や社内の第三者への相談にとどめるべきでしょう。
- 被害の詳細を記録する。(日時・場所・加害者の氏名や所属部署・加害者の言動など)
- パワハラ行為を録音・録画する。
- 現場に目撃者がいた場合は、目撃者の氏名や所属などをメモする。
- 怪我を負ったり、パワハラによるストレスで心身のバランスを崩して医療機関にかかったりした場合は、医師に診断書を書いてもらう。
- 社内で相談できる人物を見つける。(信頼できる相手であることが条件)
- 社内のパワハラ専用の相談窓口や労働組合へ相談する。
セクハラ・パワハラ被害を第三者に相談する
セクハラ・パワハラ被害が一向に収まらない場合、あるいはエスカレートした場合は、一人で抱え込んだり解決しようとしたりせず、専門家に相談することをおすすめします。
都道府県の総合労働相談コーナー
全国の総合労働相談コーナーでは、セクハラ・パワハラ被害に関する相談の受付けや、職場の様々なトラブルの解決の支援を無料で行っています。
関連リンク; 都道府県別の総合労働相談コーナー
法律事務所に相談する
法律事務所では、損害賠償請求や刑事告訴など、法的措置に関する相談やアドバイスが受けられます。ただし、証拠がないと会社や加害者本人の民事・刑事責任を問うことはほぼ不可能です。
また、法律事務所では証拠収集は行わないため、法律事務所を通して提携の探偵事務所に委託するか、被害者自身で探偵事務所を探す必要があります。
探偵事務所に相談する
SAT探偵事務所では、あらゆる合法的な調査方法を組み合わせた調査力に強みがあります。弁護士などとも連携して対応することが可能なので、セクハラやパワハラの被害者が取るべき対応についてもアドバイス可能です。
告訴や民事・刑事訴訟の際、被害を立証できる証拠集めなら、探偵事務所に依頼することをおすすめします。また、法的手段を検討している場合は、提携弁護士を無料で紹介できるSAT探偵事務所にお気軽にご連絡ください。
セクハラ・パワハラに対する法的措置には「被害を立証する証拠」が重要

セクハラ・パワハラの被害者が加害者を刑事告訴したい場合や、加害者・勤務先企業に損害賠償請求を検討する際、「被害を立証できるか否か」が告訴の受理や裁判を有利に進めるための鍵となります。
そこで、ここからはセクハラ・パワハラを立証するために、どのような証拠を集めるべきかをご紹介します。
セクハラ被害を訴える際に有力な証拠とは
セクハラ被害の有力な証拠は、被害内容を客観的かつ具体的に証明できるものでなければなりません。被害を立証するうえで必要となる証拠は以下のとおりです。
物的証拠
- 被害者の日記やメモ(日付・場所・加害者の氏名や所属部署・行為の内容などの詳細)
- 加害者とのメール履歴
- 加害者との会話の録音
- 加害者からの手紙やプレゼント
- セクハラ行為の録画映像(隠しカメラなど設置可能な場合に限る)
- 医師の診断書(セクハラによるストレスが原因で心身のバランスを崩し、医療機関を受診した場合)
人的証拠
- 同じ人物からセクハラ被害を受けている社員がいる場合は、その人物の証言
- 目撃者がいた場合は、その人物の証言
パワハラ被害を訴える際に有力な証拠とは
パワハラ被害の立証においても、客観的・具体的に被害を証明できる証拠収集が必要です。労働紛争や裁判を有利に進める際、これらの証拠を用意しておくと良いでしょう。
物的証拠
- 被害者の日記やメモ(日付・場所・加害者の氏名や所属部署・行為の内容などの詳細)
- 加害者とのメール履歴
- 加害者との会話の録音
- SNSやインターネット掲示板上の当該パワハラ行為に関する書き込み(URLと書き込み内容のスクリーンショット)
- パワハラ行為の録画映像(隠しカメラなど設置可能な場合に限る)
- 医師の診断書(セクハラによるストレスが原因で心身のバランスを崩し、医療機関を受診した場合)
人的証拠
- 同じ人物からセクハラ被害を受けている社員がいる場合は、その人物の証言
- 目撃者がいた場合は、その人物の証言
セクハラ・パワハラの証拠集めは探偵=専門家に依頼する

セクハラ・パワハラ被害を刑事告訴あるいは損害賠償請求する際、重要な鍵となる証拠の中には、セクハラ・パワハラの現場の映像や、同様の被害を受けている他の社員の特定、さらにはその人物からの証言の入手など、被害者が個人レベルで入手するのが困難なものもあります。
セクハラやパワハラの被害に悩み、解決のためにも確実な証拠を押さえたいという方におすすめしたいのが、探偵事務所のセクハラ・パワハラ調査です。
そこで、ここからは探偵事務所のセクハラ・パワハラ調査の調査方法や、探偵に依頼するメリットなどを徹底解説します。
探偵のセクハラ・パワハラ調査方法
探偵事務所のセクハラ・パワハラ調査では、依頼人の勤務先への潜入調査、関係者への聞き込み、インターネット調査、加害者の素行調査などが行われます。それぞれの調査内容について詳しく見ていきましょう。
依頼人の勤務先への潜入調査
探偵事務所の調査員が正体を隠して、依頼人の勤務先に潜入して直接証拠を集める手法です。セクハラ・パワハラ調査の潜入調査では、社内で流れるセクハラ・パワハラに関する噂や、加害者に関する風評を聞き出すことはもちろん、加害者に直接接触して情報収集を行うことも可能です。
ただし、調査員の身元が明らかになってしまうと調査自体が失敗に終わりやすい、というリスクを孕むため、調査は慎重に実施する必要があります。また、調査員は依頼人の勤務先の社員・従業員として採用された上で潜入するため、潜入調査を開始するまでに準備期間が必要なケースもあります。
被害者や加害者の関係者からの聞き込み
調査員が被害者および加害者の関係者に聞き込みをかけてセクハラ・パワハラの噂を聞き出したり、目撃者の有無を調べたりすることで、セクハラやパワハラの立証へと繋げます。嫌がらせ行為の目撃者がいた場合は、さらに詳しく聞き込みを行い、被害者と加害者の特定や、日時・場所・具体的な行為の内容などを明らかにします。
聞き込みは加害者に関する噂や風評などの情報を得られやすいのが利点です。ですが、聞き込み対象者が調査内容を他人に漏らしてしまうことで、セクハラ・パワハラ調査の実施に気づかれることもあるため、聞き込み対象者や加害者に気づかれないよう慎重に行います。
インターネット調査
近年、探偵事務所への依頼が増加しているのが、ウェブサイトやSNS上での情報収集を行う「インターネット調査」です。インターネット上の掲示板やSNSは匿名での書き込みができるため、セクハラ・パワハラの加害者や目撃者が嫌がらせ行為について何らかの書き込みをしている可能性があります。
加害者の素行調査
素行調査とは、セクハラ・パワハラ加害者の日頃の素行を調べることを目的として行われる探偵の調査です。
セクハラ・パワハラの加害者が「いつ・どこで・誰と・何をしていたか」を監視して、それらを記録に残したり、写真・映像に収めたりします。素行調査の基本は尾行と張り込みで、調査は加害者の出勤日に限らず、休日やプライベートでの過ごし方についても実施されます。
素行調査では、加害者の行動・生活・収支や財産状況・嗜好・プライベートなど、加害者の行動や人物像を徹底的に調べます。調査そのものの時間軸は現在に限定されるものの、素行調査を進めるうちに、加害者が過去にも同様の嫌がらせをしていた事実が明るみに出ることもあります。
セクハラ・パワハラ調査を探偵に依頼するメリット
セクハラ・パワハラ調査を探偵事務所に依頼することで、告訴や裁判の時に被害を立証しやすくなることはご理解頂けたのではないでしょうか。
探偵事務所にセクハラ・パワハラの証拠集めを依頼するメリットは「証拠収集力」だけではありません。そこで、探偵事務所にセクハラ・パワハラ調査を依頼するメリットを整理しました。
被害者自身が直接調査に関わらずに済む
セクハラ・パワハラの加害者が、直属の上司・先輩・同僚など、職場で日頃から接する機会が多い人物であった場合、被害者自身が証拠を集めようとして、加害者に必要以上に接触せざるを得ない状況も起こり得ます。これにより、被害者の精神的な負担やストレスが増強されるだけでなく、さらに嫌がらせ行為を受けるリスクを伴います。
一方で、第三者である探偵事務所に調査してもらうことで、被害者は必要以上に加害者と接触せずに済むため、自ら証拠収集する時よりも負担やストレスを軽減することができるのです。
セクハラ・パワハラへの対処の仕方をアドバイスできる
探偵事務所はセクハラ・パワハラ調査の実績や様々な調査ノウハウを保有しているため、被害者の相談内容に応じて適切な対処方法をアドバイスできます。
提携弁護士との連携がスムーズ
パワハラ・セクハラの証拠が集まり、加害者に対する民事・刑事訴訟の段階に進むと、法律の専門家による助言やサポートが必要になります。
探偵事務所であれば、セクハラ・パワハラ訴訟に精通した提携弁護士の無料紹介が可能で、調査の段階から探偵と弁護士の連携もスムーズになります。
「個人情報保護義務」や「秘密保持義務」によって依頼人のプライバシーが守られる
探偵事務所にセクハラ・パワハラ調査の依頼を検討する時に懸念されやすいのが、被害者自身のプライバシーや個人情報の漏洩リスクです。
都道府県公安委員会に届出済みの探偵事務所は、探偵業法に則って依頼人の個人情報やプライバシーを外部に漏らしてはならない、また、調査で得られた情報はすべて適切に取り扱わなければならない(探偵業法第8条3項、第10条)、という義務を負っているため、被害者のプライバシーは保護されます。
まとめ
セクハラやパワハラの加害者や会社を訴えたいという場合、セクハラ・パワハラ行為を証明することが告訴や裁判では絶対不可欠です。
とは言え、被害者自身による証拠収集にはいくつものデメリットやリスクがあるため、セクハラ・パワハラ調査は探偵事務所に相談すべきである、という点をご理解頂けたのではないでしょうか。
なお、自身は嫌がらせの被害者でなくとも、セクハラ・パワハラが横行する社風や職場環境を改善したいが、具体的に何から着手すれば良いかわからない場合や、部下や同僚が嫌がらせを受けている様子が見られ、何らかの対処を検討している場合も、ここでご紹介した内容を参考にしてみて下さい。
警察OBに直接相談できる探偵事務所
受付時間/10:00~20:00
※LINE相談は友達登録をして送られてくるメッセージに返信することで行えます。