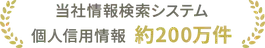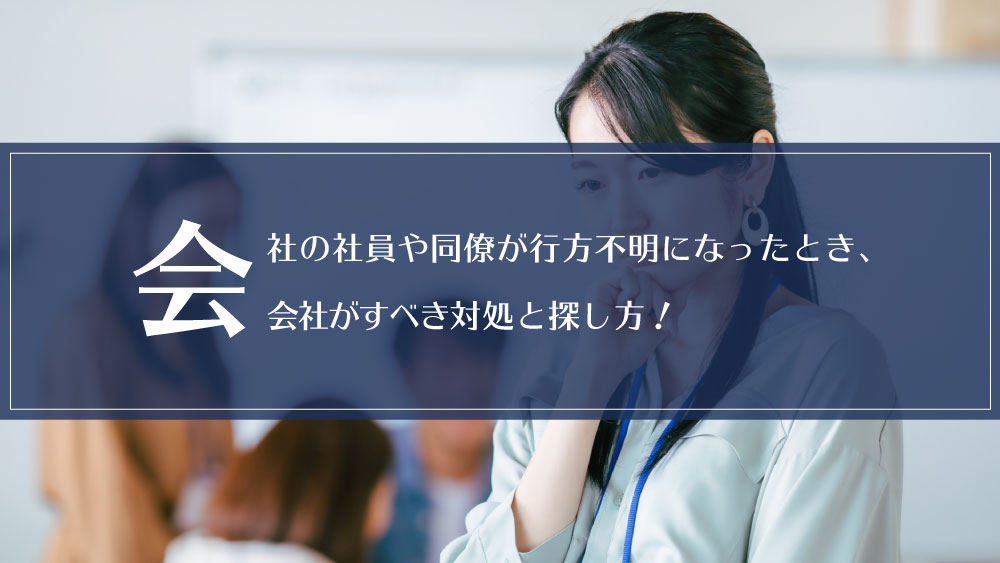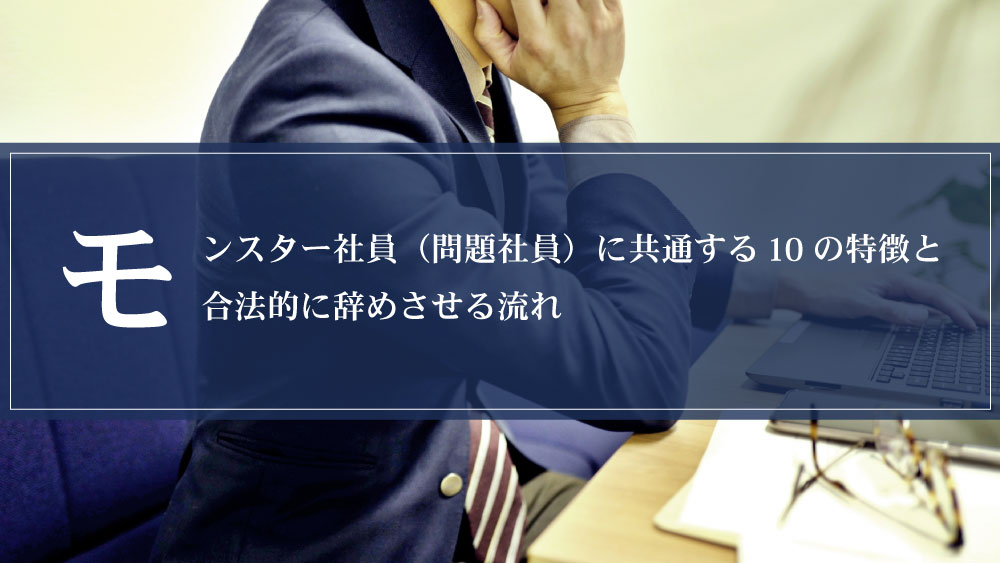サッと読める!
ためになるSATコラム
カテゴリーで絞り込み
個人向け調査
社員の副業を理由に解雇はできる?過去の判決例から考察
【投稿日】2022年9月23日

企業として社内規則で副業を禁止している場合、社員の副業実態が気になることでしょう。
果たして、副業が発覚した社員はどのように処分されるべきなのでしょうか。また、副業がバレたら社員を解雇してもいいのでしょうか。
実は、副業をしているかどうか程度では、従業員は簡単に解雇できるものではありません。
そこで本記事では、それでも解雇できるケースとしてどのようなことが考えられるのか、またその際に注意すべきことはなにかについて、過去の裁判事例なども交えながら解説します。
そもそも会社が社員の副業を禁止にできる権利はあるのか?
「副業禁止」という会社がまだ多数を占める日本ですが、そもそも企業側が雇用している従業員個人の副業を禁止していい権利はあるのでしょうか。まずはその点から考えることが重要です。
厚生労働省が副業を奨励!SDGsの波も
近年ではSDGsへの取り組みが活発化したという社会背景があり、働き方改革やダイバーシティなど、より持続可能な働き方が注目され、尊重され受け入れられるようになりました。
そんな中、厚生労働省は令和2年に副業・兼業の普及促進案をガイドラインとして打ち出しました。
ガイドラインによると、以下の文言がこれからの社会における副業の可能性について象徴的に示唆しています。
2 副業・兼業の促進の方向性
(略)
(2) 人生 100 年時代を迎え、若いうちから、自らの希望する働き方を選べる環境
を作っていくことが必要である。また、副業・兼業は、社会全体としてみれば、
オープンイノベーションや起業の手段としても有効であり、都市部の人材を地方
でも活かすという観点から地方創生にも資する面もあると考えられる。
また、社員の副業に対して企業がどのようなスタンスを取ることが推奨されるかについては以下のように記載されています。
3 企業の対応
(1) 基本的な考え方
裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である。
副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業務に
支障をもたらすものかどうかを今一度精査したうえで、そのような事情がなけれ
ば、労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業
を認める方向で検討することが求められる。
実際に副業・兼業を進めるに当たっては、労働者と企業の双方が納得感を持っ
て進めることができるよう、企業と労働者との間で十分にコミュニケーションを
とることが重要である。なお、副業・兼業に係る相談、自己申告等を行ったこと
により不利益な取扱いをすることはできない。
本項によると、社員の副業を認めることが企業の基本的なスタンスであると、ガイドラインでは示されています。
さらに、ガイドラインの制定に伴いそれまで、厚生労働省が公表していた「モデル就業規則」に記載されていた「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という一文が削除されています。
このように、世の中はかつての副業禁止スタンダードから副業スタンダードの風潮へと大きく変わってきているのです。
副業の意義、価値が変わってきた
厚生労働省による副業の奨励や、大手企業の副業解禁などの発表もあり、世の中の副業に対するイメージは刷新されてきています。
具体的に、それは、副業という言葉が持つ意味は単なる「お金稼ぎ」にとどまらなくなったことを意味しています。
近年では副業について語られる場合に「複業」「兼業」といった表現も用いられるようになってきました。
社会参加する個人がそれぞれどのように自己実現するか、どのように技術を研磨すれば社会参画できるかを探る手段ともなっていて、一人の人生に密接に関わるのが現代の副業と言えます。
例えば、外出自粛下の影響でSNSやデジタルプラットフォームが進化し、スマホひとつあればライブストリーミング(配信業)を気軽に行える環境が整えられるようになりました。
ライブ配信は少額ながら収益化が可能であり、アーティスティックに自己表現をしつつ収入が得られる業態です。配信業は、業務命令権の範囲外である就業時間外に行われるのが一般的であり、会社側が口出しできるものではありません。
他にも、フードデリバリー業は飲食物を配達する代表的な副業として確立されています。自転車やバイクを使って配送するケースが多く、趣味の運動と実益を兼ねた副業と言えるでしょう。
このように、副業に対する社会的意義や価値事態が変わってきたという点も大きなポイントです。
副業を理由にして解雇できるケースとは?
社員と雇用契約を結ぶと、業務時間内は業務命令権が及ぶ範囲だと考えられます。
そのため業務時間内に本来の業務と関係がないことが実行されていた場合、業務命令違反として社員を解雇するための大義名分が得られると考えることはできます。
このように社員の行動に制限をかけたり、解雇する場合には労働契約において就業規則を遵守させる内容とする必要があります。
副業が行われることで、会社本来の業務に支障をきたすなど「会社に迷惑をかける」のであれば禁止行為にできるためです。
ただ、その際も「禁止する必要性が高い業種に限定する」など工夫をこらさなければ、法的効力を付随させることは難しくなります。
それではどのような場合に、副業を理由に解雇が成立する可能性が高いのかを解説します。
ケース1:業務時間中なのに副業された場合
雇用契約に記載された就業時間は、当該業務に専念しなければならない義務が生じます。これを「職務専念義務」といいます。
労働契約上は、給与とは一定時間実際に働いたことへの対価として支払われることになるためこの義務が付与されるのです。
つまり、当該業務の契約上定める業務時間内に、全く何の関係もない副業をされた場合には業務命令違反として解雇につながる可能性が浮上します。
ケース2:本業にネガティブな影響を及ぼす副業の場合
副業をしていることが、本業に深刻な悪影響を与えている場合は禁止とすることができる可能性があります。
例えば副業を本業の時間外にしていたとして、その労働時間があまりにも長く十分な休養が取れず、本業に遅刻したり本業の業務時間内に寝てしまったり、一切身体が動かなくなるなどしてしまえば本業に支障をきたしていることになります。
この場合、本来契約したはずの労働が提供できなくなっている状態であるとされ、注意や指導による改善の期待など、譲歩の余地を残しつつ懲戒や解雇のフェーズに進むことが考えられます。
ケース3:競合他社で副業を行っている場合
社員の副業が、全く同じようなジャンルの業種である企業であるような場合も解雇が成立することがあります。
それは社員が負う競業避止義務(在職中の競業禁止)により、会社に損を与える行為をすべきではないと解釈されるためです。
本業で得た知識を同業の副業先で利活用した場合、本業の会社が本来得られたはずの利益が得られなくなる可能性もあります。この場合、損害賠償の成立にもつながります。
ケース4:副業により、情報漏洩が起こりうる場合
ある社員が副業を通じて社内機密情報を流出させてしまう場合、その副業を禁止したり結果如何により解雇が成立することがあります。
例えば最新技術や顧客の個人情報、流通経路など本来社外秘であって然るべき情報を何かしらの媒体で公開することにより収入を得る形態の副業をひとりの社員が行っていた場合、社内外の関係各社、ステークホルダーすべてに迷惑をかけることになります。
こういったケースであれば、副業を禁止することが会社の利益を守ると認められるのです。
ケース5:副業により、本業の企業が社会的信用を落とすことになる場合(副業内容が違法な場合)
社員の一人が携わった副業により、本業の企業が社会的信用を失うことになるのであれば、当該社員を解雇することでその尊厳を守ることが必要になります。
また、副業の内容が反社会的であったり、法律違反に関わることであるなどで、マスコミなどに報道されてその社員が本業の企業の従業員だと発覚すれば、本業の会社のイメージが崩れます。
ただ、どういった内容の副業であれば一律で解雇できるかといった基準は存在しません。本業の知名度や業種、規模により左右されます。
どういう手順で副業発覚から解雇に至るのか?
副業により深刻な被害があった際には解雇を行いますが、それでもまずは本人への注意や指導を行ったり、いきなり解雇させることは難しいのが現状です。
具体的に副業が発覚し、本業への悪影響など重要な社内規則違反が発覚した場合、どのように従業員への対応を進めていくのでしょうか。一般的な手順は次の通りです。
STEP1:本業へ悪影響が出ていることへの注意と指導をする
本業に深刻な悪影響を及ぼす副業が発覚したら、まず本人への注意と指導をすべきとされています。
それは「本人への対話」という形の企業努力によりその被害を低減させられるかも知れず、即刻の解雇よりも対話を重ねたほうが妥当な手段であったと見做されることがあるためです。
また今後いずれかの時期での解雇を視野に入れていた場合でも、適切な頻度での注意や指導は必要です。注意も指導もしていなかったのに、いきなり会社が副業により被害を受けたから解雇したいと申し出ていても、それ以前の状況を会社側は受け入れていた、つまり副業を黙認していたと見做されるためです。
副業をしている当人へ注意する際には、状況改善を求めます。それもいきなり副業をやめることを命令するというものではなく、どのような悪影響が本業に出ていて、それを改善してほしいという言い方がベターです。
上記のように本業に悪影響が出ていることを示す注意の内容は記録して残しておけば、解雇の際に解雇たる論拠となることもあります。逆に記録していなければ、本業への被害がない副業を理由としての解雇と見做されてしまい、状況が不利になります。
これまで解説したように、本業への差支えがない副業なのであれば解雇事由としては成立しなくなります。禁止すら強制できません。
STEP2:状況が改善しなければ懲戒処分を実行
本業に生じている悪影響をなくすように注意を繰り返しても、当該問題がなくならないようであれば懲戒による処分を実行します。
懲戒処分の種類は、以下の通りです。
- 戒告:口頭で厳重に注意をすること
- 譴責(けんせき):始末書を提出させ、今後同じ理由で職務遂行に支障をきたさないよう、将来を戒めさせること
- 減給:賃金から一部の金額を差し引くこと
- 出勤停止:一定期間、出勤を禁止させること(同期間の賃金なし)
- 降格:役職や職位、職能資格をそれまでのものより下げること(役割の失効に応じて給与も下がる)
- 論旨解雇:退職願の提出を勧めること
- 懲戒解雇:一方的に解雇すること
悪影響が出ている状況への程度を鑑みて、適切な処分を下さなければその処分が不当とされてしまいます。
副業により遅刻したり、就業時間に寝ていた程度で減給以上の処分をしてしまうのは早計です。
同業他社への関わりのような副業により、当社側に情報流出など深刻な被害が生じている場合に解雇できるといった前段落までの例は、本項における懲戒解雇などが成立した例です。
STEP3:解雇前には論旨解雇(退職勧告)を実行
前項における解雇系の重い処分を行う場合は、副業により深刻な悪影響が本業に及んでいる場合であると考えられます。
この場合もまずは合意退職・希望退職となるように、副業をしている社員の今後の人生において有益に事が運ぶように仕向けるようにします。この時は退職合意書を作成して、以後のリスクを起こさないようにする対策をすることがポイントです。
つまり、まず本人との対話、説得の機会を設けましょう。本業に支障をきたすほど副業に入れ込んでいるのであれば、そちらで生計を立てたほうが当人の今後につながるのではないかといった理解を態度で示します。
副業を行っている本人のモチベーション的にも、そもそも本業と捉えているはずの側における就業時間を適当に扱えなくなっているのであれば、すでに本業への思い入れ、ロイヤリティは失われているはずです。
退職勧告が通じない場合に初めて懲戒解雇へと進むことになります。
副業が理由でも解雇できないケースとは?
いくら就業規則で副業に関する規定を示しても、それに違反したからといって確実にすぐさま解雇が成立するわけではありません。
それでは本章では副業を理由として解雇できないケースについて解説します。
ケース1:副業が本業の妨げになっていない場合
労働契約法16条によれば、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合の解雇は解雇権濫用法理というルールが適用され、不当解雇とみなされることがあります。
解雇できるのは、本業への支障が明らかであるときになります。つまり副業をしている本人がきちんと時間管理をし、業務時間外に副業を行い本業への影響も生じさせていないのであれば、解雇どころかどのような懲戒事由にも該当しません。
また本業に支障をきたしていると会社側が一方的に判断しただけでは効果は薄いことがあります。そのような曖昧な状態で解雇を通達しても、不当解雇や不当処分の扱いを受けて終わりなことも。争ってでも解雇したい場合でも、最低限、解雇理由証明書などを揃えておくべきです。
また係争で負けた場合、以後は副業をきっぱりと認めなければならない結果となることもあります。
ケース2:副業を黙認していた場合
ほか副業の実態を会社側が把握していながら、黙認していた場合でも副業を理由とした解雇は成立しないことがあります。
黙認していたのであれば、事実上副業を許可しており、業務に支障がなかったと見做されることがあります。
ケース3:副業についての微細な判断をせず一律禁止としていた場合
これまで見てきたように、副業は本業に支障をきたすほどの内容となって初めて解雇の理由のひとつと位置づけられる可能性が浮上するものでした。
このため、就業規則として一律で副業を禁止してしまい、そちらを理由に解雇しようとしても、当該副業の実態として本業への影響が限りなく小さかった場合などは不当解雇と扱われたり、就業規則事態が適法と見做されなくなる可能性が高いです。
副業を禁止したい、副業を理由に解雇したい企業が気をつけるべきこと
これまで解説してきたように、副業イコール即時解雇という図式はまず成立しません。まずこのことを理解し、万が一副業を発見した時の立ち回りをどうすべきかについて知っておきましょう。
企業が、従業員の副業発覚時に気をつけたい注意点について解説します。
【1】副業を禁止にするより、許可制にして懲戒解雇事由に記載したほうがベター
社員の副業を禁止するには、労働契約に「副業禁止」を盛り込まねばなりません。労働契約の内容は雇用契約書や就業規則に記載しなければならないほか、10人以上の従業員が雇用される現場では就業規則を労働基準監督署へ提出する義務があります。
ただ本来、副業を禁止する法的効力を企業側は持ち得ていないため、労働基準監督署の心証がどうなるか、その有効性は裏付けられないことを留意すべきでしょう。
その点、副業を許可制にする場合だと、禁止よりも社員にとって制約が少ない状態であるため有効性が高くなります。
同時に副業関係の違反についてを懲戒解雇事由に記載します。また、いざ懲戒解雇をする場合には、懲戒解雇を進めるための一連の手続き(懲戒委員会設置、弁明機会付与など)を明確にしておかなければなりません。
【2】相当悪質な副業実態がなければ退職金取り消しはない
懲戒解雇に関する判例では、それまでの継続した勤務・労働を相殺したり減衰させるほどの背信行為がなければ退職金を削ることすらできないという判断が示されています。
就業規則に「懲戒解雇時の退職金支給なし」を記載する企業がありますが、一方的に示しても法的効力は生まれません。
このため、解雇すなわち退職金なしと楽観的に捉えるのは非常に危険です。
【3】副業にも利用できるメリットはある。残業代には注意
副業は、企業にとってメリットもあります。これまでの解説で、相当に深刻な被害がなければそもそも副業のあるなし程度で即刻の解雇は非現実であるということは理解いただけたと思います。
逆に副業を自社のために利用してみるというのも1つの手です。
従業員による副業のメリットとは以下の通りです。
- 一社の文化に留まらない多様な社会経験ができる
- 日本にありがちなリーダーシップ型雇用では得られない、他ジャンルの職務経験ができる
- 上記の経験を自社業務にフィードバックできる
- 自社にも利活用できるかもしれない人脈が得られる可能性がある
- 副業は会社の助けを借りることができないため自己管理能力を鍛えられ、本業への責任感を養うことができる
このように副業で得た経験は、自社に全くの不利益しかもたらさないとも限りません。
副業を有効に利用するためには副業ルールの設定も推奨されます。
中途半端に副業を禁止していたりと社員に対して何かしらの制約をかけてしまっている場合、もし仮に他者が副業をしていることが(会社に一定の利益をもたらすからと)見逃されていると別の社員が見つけた場合、不平等を感じることがあるでしょう。
そういったリスクを避けるためには就業規則の中に副業規定などを新設すべきです。
また気をつけたい部分として副業を解禁、許可制を導入すると従業員の労働時間は本業と副業で通算されて計算されることがあげられます。
このため、従業員の合計労働時間が法定労働時間の8時間/日、40時間/週を越えた場合、企業側は割増賃金として残業代を支払う義務が発生することは覚えておきましょう。
副業が理由の解雇が裁判となった例を解説!
ここからは、副業を禁止する規則に反したため解雇になったケースが裁判に発展した際の判例について解説します。解雇が有効だったのか、無効だったのかに注目してください。
過去に裁判所は副業に関する解雇についてどのような点を重視しているのでしょうか。
【判例1:有効】小川建設事件(東京地裁昭和57年11月19日決定)
小川建設事件とは、兼業が許可制だったものの無許可でキャバレーで働いた社員を解雇したというもので、解雇処分が有効だと判断されました。
解雇が有効となった理由は、キャバレーの勤務時間こそ本業とは重なっていなかったものの、深夜6時間の激務により本業に支障をきたしていたことにありました。また就業規則では本来懲戒解雇処分が適当とされていながら、合意の解雇の形を取っていたことも考慮されたようです。
【判例2:無効】十和田運輸事件(東京地裁平成13年6月5日判決)
十和田運輸事件では配送業者社員が勤務時間中に、払い下げられた製品を他部署と半有して利益を得て、当該行為に社用車が使われたことで懲戒解雇となりました。
しかしながら当該行為の頻度が年に1~2回、しかも本業に支障がなく黙認状態であった下地があり、解雇が無効となりました。
副業での解雇は簡単にできないのが現状!解雇をするためには正当な理由と証拠が必須!
本記事では、副業をしている社員を解雇するには、というテーマで解説しましたが、社内規則に「副業禁止」と書かれていたとしても、そう簡単には従業員を解雇できないのが現状です。
過去の裁判例でも、副業により相当に深刻な被害を本業にもたらしていないのであればその解雇が就業規則で規定されていたとしても無効とされることがわかります。
もし、企業が社員を副業により解雇したいと思った場合には、解雇をするに至る正当な理由や証拠集めが重要となります。
副業は、社員がプライベートの時間で行っていることが多いので、それを調査をしようとすると個人情報保護法などに違反してしまう可能性があり、非常にリスキーです。
もし、副業により会社にとって不利益を与えている怪しい社員がいる場合には、自社内で調査するよりも、探偵業法に基づき個人への調査が行える探偵事務所への相談がおすすめです。
探偵事務所SATでは、社員の副業の実態調査なども承っております。まずは、メールや電話などでご相談ください。
警察OBに直接相談できる探偵事務所
受付時間/10:00~20:00
※LINE相談は友達登録をして送られてくるメッセージに返信することで行えます。