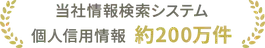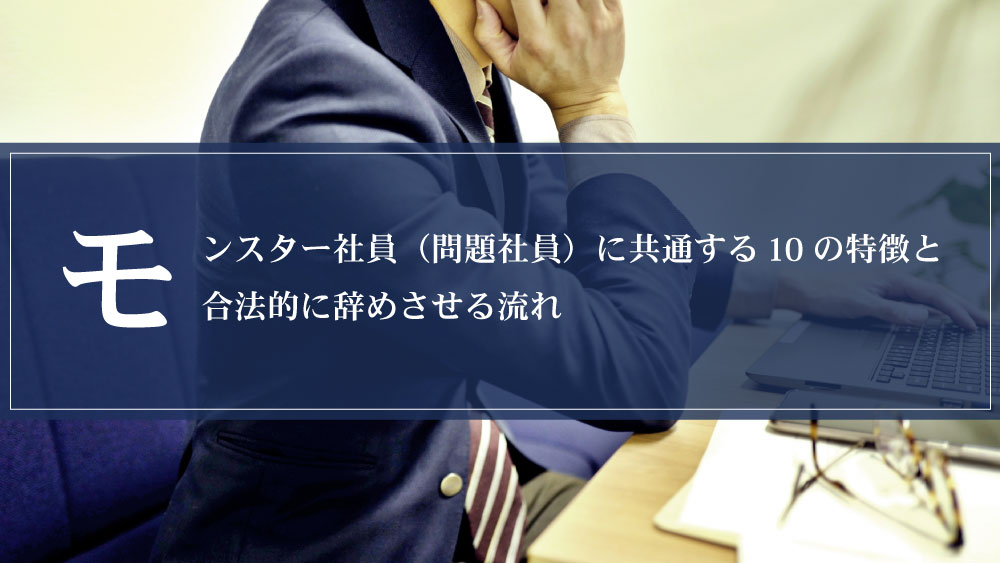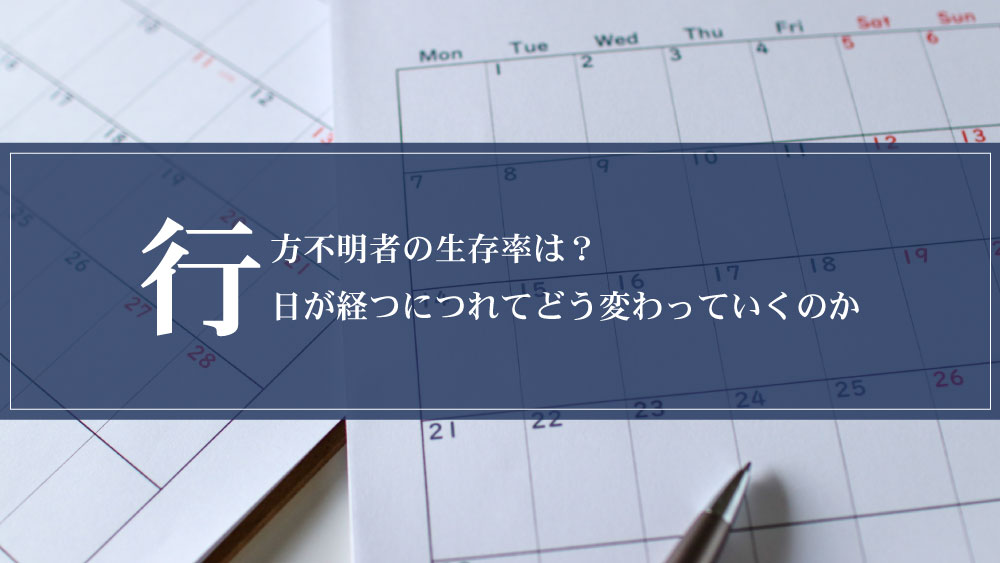サッと読める!
ためになるSATコラム
カテゴリーで絞り込み
個人向け調査
嫌がらせ・イタズラは何罪で逮捕できる?刑事告訴する手続きと必要な証拠
【投稿日】2026年1月25日
- 嫌がらせやイタズラも、証拠が揃えば刑法に触れる罪として刑事告訴できる可能性があるが、警察は証拠がないと受理しにくい。
- 犯人の特定・逮捕につながる確実な証拠(映像・写真・音声など)は自力では集めにくく、プロの技術が必要である。
- 探偵なら警察の捜査を動かす材料となる証拠収集を合法的に行い、刑事告訴・訴訟など次のステップへの準備を支援できる。

嫌がらせやイタズラには色んな解決法がありますが、その中で最後の手段ともいえるのが、犯人に対する刑事罰を求める刑事告訴(告発)です。
実際そこまでこじれることはそう多くはありませんが、初手から告訴も視野に入れて調査をしておけば、後々の不安を予防することもできます。
そこで嫌がらせ・イタズラが具体的にどのような罪に当たるのかと、それぞれの罪で犯人を刑事告訴するために必要な証拠や手続きについて、基礎から丁寧に解説します。
嫌がらせ・イタズラ自体が罪でなくとも、その過程で何らかの罪を犯している可能性は充分にあるので、そういったケースも想定してご自分の遭った被害と照らし合わせてください。
嫌がらせ・イタズラの被害を警察に訴える!刑事告訴・刑事告発・被害届の違い

警察に被害を訴える方法には、刑事告訴・刑事告発と被害届があります。
違いがよくわからないという方も多いでしょうが、目的も警察の対応も違うものです。まずはその違いを説明します。
受理・捜査義務と提出できる人
| 目的と内容 | 警察が受理する義務 | 警察の捜査義務 | 提出できる人物 | |
|---|---|---|---|---|
| 被害届 | 犯罪の被害を申告する | あり | なし | 被害者か親族(告訴権者)、あるいはその代理人弁護士 |
| 刑事告訴 | 犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める | 法的にはない | あり | 被害者か親族(告訴権者)、あるいはその代理人弁護士 |
| 刑事告発 | 犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める | 法的にはない | あり | 制限なし |
まず被害届は、どんな被害があったのかを警察に申告するだけのものです。管轄の警察署や交番に申し出れば、警察官が一緒に作成してくれます。
また、警察には被害届を受理しなくてはならないという義務があります(参考:e-Gov犯罪捜査規範第61条)。
しかし受理したからといって、犯人逮捕につながるよほど有力な情報がない限り、警察が積極的に捜査してくれることは稀です。特に嫌がらせ・イタズラは軽犯罪にあたる場合が多いため、どうしても凶悪事件が優先されてしまいます。
被害届を受理しても、警察に捜査の義務は生じないのです。
[br num=”2″]
対して刑事告訴・刑事告発は、受理されれば警察には事件処理の結果を通知する義務が生じるため、捜査しなくてはなりません。ここが被害届との大きな違いです。
また告訴と告発の違いは、「誰が訴えるか」にあります。告訴権者本人が訴えれば告訴、それ以外の人間が訴えれば告発です。告訴権者とは、被害者やその親族などを指します。
例えば脱税や公務員の不正など公の利益を害する重大な犯罪の場合は、告訴権者以外による告発が可能です。(参考:e-Gov刑事訴訟法第239条)
嫌がらせは比較的軽い犯罪に類することが多く、かつ第三者が告発することで被害者の利益を損なう場合もあります。よって告訴の形をとるのが一般的です。(参考:e-Gov刑事訴訟法第230条)中でも親告罪に類するケースでは、告訴権者以外が告訴することはできません。親告罪とは、告訴権者のみが告訴できる罪のことです。
嫌がらせ・イタズラは何罪にあたる?罰則は?

嫌がらせ・イタズラといっても、証拠さえそろえば告訴して罪に問えるものはたくさんあります。どんな罪があるのか、その罰則とともに見ていきましょう。
「器物損壊罪」自転車や車やポストなどを壊す、ペットを傷つけるなど
器物損壊罪は、他人の所有物(ペットなどの動物含む)を壊す・傷つけるなどの罪です。3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(参考:e-Gov刑法第261条)
例を挙げると、車や自転車を壊される、ペットにいたずらされる、あるいはポストやドアを勝手にこじ開けられた場合などがこれにあたります。嫌がらせ・いたずらの多くに適用できる罪です。
「窃盗罪」自転車・洗濯物・手紙やそのほか持ち物の持ち去り、無断使用など
窃盗罪は、他人の所有物を故意に持ち去ったり無断で使用したりする罪です。10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。(参考:e-Gov刑法第235条)
嫌がらせには洗濯物や手紙を盗むものも多いため、適用されることの多い罪の1つです。
「信書開封罪」ポストから手紙を盗んで勝手に開封する
他人のポストを漁って手紙を勝手に開封した場合は、信書開封罪に当たります。手紙を盗んだかどうかは関係ありません。
信書開封罪の罰則は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金です。(参考:e-Gov刑法第133条)
「住居侵入罪・建造物侵入罪」嫌がらせのための他人の敷地・住居への侵入など
住居侵入罪・建造物侵入罪は、他人の住居・邸宅・敷地内に許可なく侵入する罪です。犯せば3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。(参考:e-Gov刑法第130条)
嫌がらせはターゲットの敷地内に入って行われる場合がほとんどです。かつ住居侵入罪・建造物侵入罪は未遂罪といって、実際に侵入を実行しなくても計画しただけで問われる罪です。そのため、嫌がらせの多くの場合に適用できます。
「名誉棄損罪・侮辱罪」悪い評判を広める、事実無根の怪文書をばらまくなど
この2つは大雑把に言えばどちらも他人の悪口を公に広める罪であり、混同されがちですがはっきりとした違いがあります。
- 名誉毀損罪:公然と事実を示し、他人の名誉・社会的評価を貶める罪(参考:e-Gov刑法第230条)
- 侮辱罪:公然と事実を示さず人を侮辱する罪(参考:e-Gov刑法第231条)
注意してほしいのは、ここで言う事実とは真実とは限らず、「〇〇さんは会社で横領した」「〇〇さんは不倫をしている」といった具体的な内容のものであれば、虚偽であっても名誉毀損の罪に問われるということです。
つまりいわゆる悪い噂が名誉毀損罪にあたり、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金に処せられます。むしろ噂が虚偽のケースの方が悪質とされ、より罰則が重くなる傾向にあります。
これに対し侮辱罪は、「バカだ」「卑怯者だ」などのストレートな罵倒に適用されます。罰則は拘留または科料と定められていますが、これは犯罪において最も軽いです。
ちなみに名誉毀損罪も侮辱罪もともに親告罪であり、被害者本人とその親族などの告訴権者しか訴えることができません。
「信用毀損罪・業務妨害罪」店の悪い噂、社会人としての悪い噂の流布
- 信用毀損罪:虚偽の内容を広めるなどして他人の信用を貶める罪
- 業務妨害罪:虚偽の内容を広めるなどして他人の業務を妨害する罪
これら2つは他人の経済的な活動を妨害する罪です。個人だけでなく被害者が経営する会社・店舗などの信用を貶めることも信用棄損罪にあたりますし、それが業務の妨げとなればもちろん業務妨害罪にもあたります。
例えば「〇〇さんの店のお弁当に使われているのは廃棄食材だ」「〇〇さんの店の商品を買ったら壊れていた」「〇〇さんは営業先のリストを元に空き巣をしている」といった嘘を広めるなどの場合です。
信用棄損罪・業務妨害罪の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
「脅迫罪」嫌がらせの手紙・メール、嫌がらせ電話、直接の脅しなど
イタズラ電話や手紙、インターネットでの書き込みなどの嫌がらせに適用される可能性があるのが、脅迫罪です。
脅迫罪は刑法222条において
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する」
引用元: e-Gov 刑法第222条
と定められています。つまり、本人や家族に対する傷害行為、監禁、所有物などへの加害をほのめかす内容が書かれていれば、脅迫罪に問える可能性は高いです。
「礼拝所不敬罪及び説教等妨害」墓地を荒らす、葬儀を荒らすなど
迷惑系YouTuberの件でご存知の方も多いでしょう。礼拝所不敬罪とは、寺社仏閣や墓地などにおいて、礼儀や敬意を失する行いをはたらいた者に適用される罪です(e-Gov 刑法第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪)。
また葬儀を妨害する行為は、説教等妨害罪にあたります。礼拝所不敬罪も説教等妨害罪も、ともに刑罰は6ヶ月以下の懲役もしくは禁錮又は10万円以下の罰金です。
礼拝所不敬及び説教等妨害にあたる行為
- 墓石への落書きや損壊
- 墓地で用を足す、汚す行為をする
- 墳墓の品位を損なうような撮影と写真の公開
(有名人の墓巡りの写真のSNSへのアップなども場合によっては当てはまる) - 葬儀の場を乱すような大声、故人に対して失礼な行為など
意外かもしれませんが墓地や葬儀を荒らす嫌がらせは多く、かつ被害者の感情を大きく傷つける行為です。目撃証言や被害を受けた墳墓の状態などを証拠として集め、しかるべき罰を受けさせましょう。
嫌がらせ・イタズラによる刑事告訴の手順・手続き

さて、嫌がらせ・イタズラといってもその多くが刑法に触れるものであることはわかっていただけたと思います。では次は、具体的な告訴の手順などについて説明します。
刑事告訴の手順・手続き
刑事告訴は口頭でもできますが、内容が複雑でありかつ証拠などの提出も必要なため、書面で行うのが一般的です。また書面作成の段階から、弁護士に依頼することをおすすめします。
告訴からの流れは以下のようになります。
1.口頭・あるいは書面(告訴状)で警察に告訴
- 告訴人の住所・氏名・電話番号などの情報と押印
- 被告人の住所・氏名・電話番号などの情報(犯人がわかっている場合)
- 犯罪事実の表示・どんな罪に触れるか
これらを告訴状に記載し、管轄あるいは告訴人か被告人の居住地の警察に提出します。
2.警察が受理すれば捜査し、事件に関する調書を作成
告訴の受理によって警察には告訴証書を作成する義務と捜査する義務が生じます。(参考:e-Gov刑事訴訟法第241条)捜査の結果、犯人が確定すれば逮捕して取り調べを行い、調書を作成します。
3.調書を証拠物などとともに検察官に送付(送検)
検察官と検事が取り調べを行い、10~20日以内に起訴・不起訴の判断を下します。
4.検察官の決定を告訴人に通達
検察官の決定には以下の4つがあります。
- 起訴:検察官が裁判所に起訴状を提出すること
- 不起訴:起訴状の提出はせず、犯人は罪に問われない
- 略式命令:裁判はせず、罰金の支払いを命じるなどの簡易的な手続き
- 処分保留:決定的な証拠がないため、犯人を釈放しての再捜査
5.公判(起訴された場合)
当事者・証人を呼んで行われる。裁判所での刑事裁判。第1回公判は起訴から約1か月後です。
6.判決
裁判により裁判官が有罪か無罪かを決定し、有罪であれば刑罰とともに判決を言い渡します。判決に不満がある場合は控訴・上告を行い、裁判のやり直しを求めることが可能です。
7.刑の執行(有罪の場合)
司法に判断を委ねるため、手続きはかなり多く時間もかかりますが、被害者(告訴人)が関わるのはここまでの流れのうち1と5のみです。告訴が受理さえされれば、捜査はすべて警察がやってくれます。
しかし問題は、警察が告訴を受理するかどうかです。これについて、次の項で詳しく説明します。
警察に告訴を受理してもらうための証拠
残念ながら、嫌がらせ程度の案件では警察は告訴の受理をためらう傾向にあります。
なぜなら告訴を受理すれば捜査して犯人を逮捕しなくてはなりませんが、それが仮に冤罪逮捕であった場合、大問題になるからです。警察としては、確実に有罪に問える証拠を集めて、犯人を確定しなくてはなりません。
捜査に人員を割くだけの結果が得られるのか、裁判で有罪に問えるのかなど、警察としても慎重な判断が必要です。そのため犯人を確定する証拠・有罪を証明する証拠があれば、警察が受理してくれる可能性は高くなります。
また警察には民事不介入の原則があるため、被害者が犯人への交渉材料としてのみ告訴を利用されては困ります。よって、告訴で犯人を刑事罰に処したいならば、民事では解決不可能であることを示すのが有効です。
嫌がらせ・イタズラで刑事告訴するために必要な証拠

刑事告訴に必要な証拠は、犯人の刑法に触れる行為を証明するものです。それさえあれば本来は、告訴状を提出することができます。
しかし警察は告訴状の受理に二の足を踏みがちなのも事実。それを動かすのに最適なものは、犯人を特定できる証拠です。
これらの証拠について、詳しく説明します。
被害状況の証拠
告訴状の説明でも触れましたが、犯人が刑法に触れる行為を行った証拠がなくては話になりません。
具体的には、以下のようなものです。
- 1. 壊されたもの(器物損壊罪)
- 2. 家の前・敷地内に放置されたもの(親書開封罪など)
- 3. 送られてきた手紙・メール(脅迫罪など)
- 4. 犯人の広めた噂などの聞き取り調査の結果(名誉毀損罪・信用毀損罪・務妨害罪など)
- 5. 日時とともに被害状況を書き留めた記録
犯行現場に残されたものや現場の保持で集めるものが主です。たくさんあるに越したことはなく、できるだけ被害時のままの状態で残しておきましょう。
また4は、素人にはなかなか集めにくいものです。特に被害者本人が聞き取りをしても本当のことを話してくれるとは思えません。是非とも調査のプロである探偵に依頼することをおすすめします。
犯人の特定に有力な証拠
犯人を特定できる証拠があれば、警察が告訴状を受理する可能性は高いです。被害届を出す場合も、犯人に目星がついていれば警察がすぐ動いてくれることもありえます。
具体的には、以下のようなものが犯人の特定につながります。
- 1. 犯人の遺留品
- 2. 指紋・声紋・筆跡鑑定の結果
- 3. 犯行現場の写真・映像・音声データなど
この中で最も有力な証拠となるのが3ですが、最も集めるのが難しいのも同じく3です。人目を忍んで行われる嫌がらせ行為を写真や映像に収めるには、探偵などのプロの技術が必要となります。
また2は、鑑定を専門に扱う民間業者がいますので、それを利用しましょう。探偵が鑑定業者を紹介してくれることもあります。
探偵や民間業者が集めた証拠はそのまま採用されるわけではありませんが、上でも説明したとおり警察を動かす材料となります。そして刑事告訴を行う際、弁護士に依頼するにも、被害状況や犯人を特定する情報がなくては、依頼を受けてもらえないこともあるのです。
嫌がらせで刑事告訴を行うために
嫌がらせは他の犯罪に比べ軽く見られがちですが、当事者にとっては重大な問題です。きっちりけじめをつけるためにも、刑事告訴を行って罪に問いたいと思う人も多いことでしょう。
ここまで解説してきたとおり、嫌がらせも大抵はいくつもの刑法に触れるため、刑事告訴して有罪になる可能性は充分にあります。しかし警察が必ずしも積極的に捜査をしてくれるわけでもなく、かつ長い戦いになるためそこまではせずに諦めてしまう人がほとんどです。
そうならないためにも、探偵に依頼して確たる証拠を集め、弁護士に依頼して万全の準備を整えるなど、プロの手を借りて臨んでください。
警察OBに直接相談できる探偵事務所
受付時間/10:00~20:00
※LINE相談は友達登録をして送られてくるメッセージに返信することで行えます。