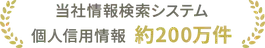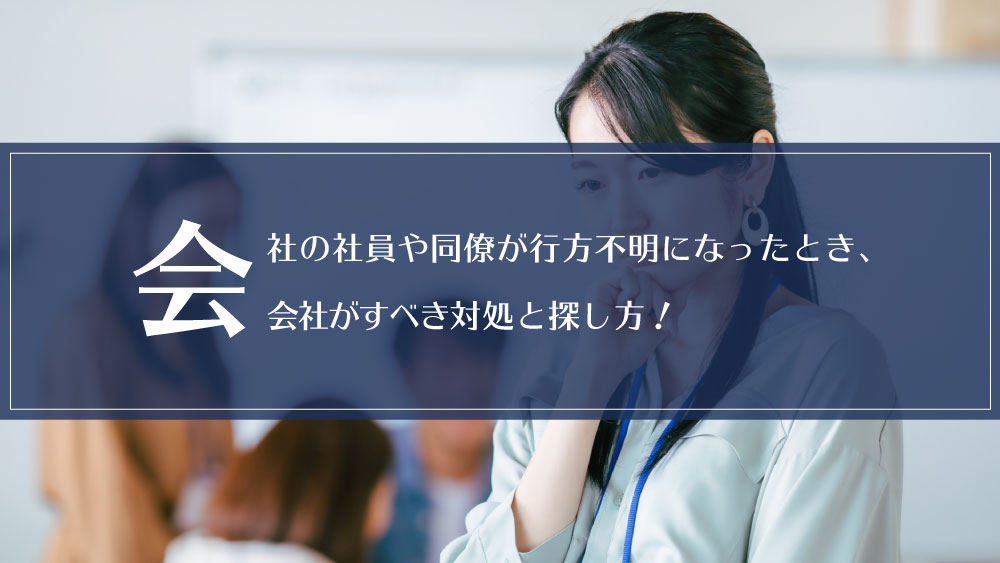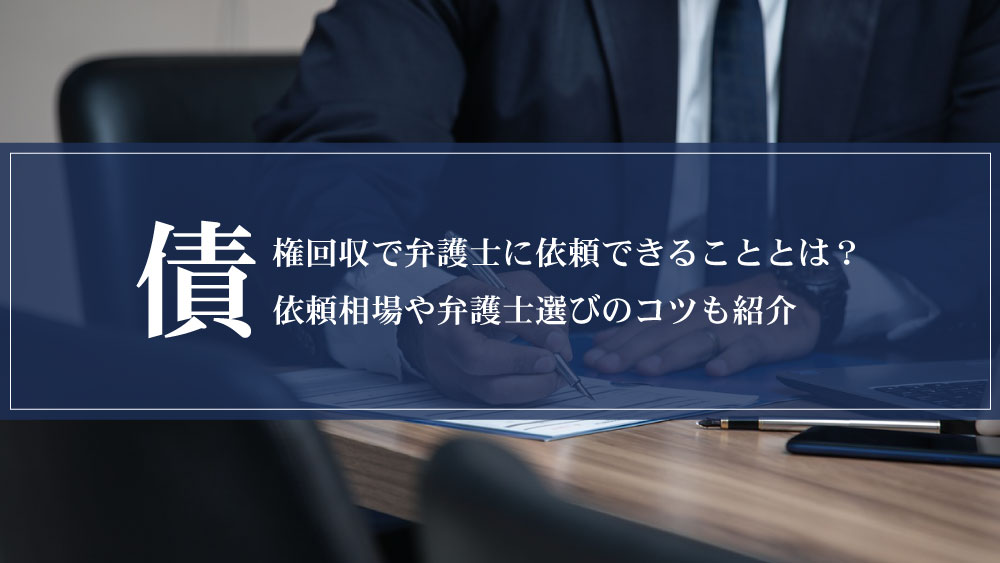サッと読める!
ためになるSATコラム
カテゴリーで絞り込み
個人向け調査
契約書なしでも工事代金の債権回収する方法
【投稿日】2025年4月14日

建て替えやリフォーム、追加工事などで、請負代金の未払いといった事態が起こることがあります。
そういった場合でも、契約書がなくても、未払い工事代金を請求できる可能性があります。
法的には、契約書がない場合でも、工事請負契約は成立するため、未払いの債権を回収することはできるのです。
つまり、正しく対応すれば、意外にあっさりと工事代金を払ってもらえる可能性はあるのです。
ただし、契約書がない場合は、請負人の側が、工事請負契約の成立や、工事代金請求権を立証しなければなりません。
そこで今回は、まず工事代金未払いの場合に取るべき対処法について解説します。
次に、契約書がなくても工事代金請求権を立証する方法を紹介し、未払いの工事代金を回収する方法、さらに工事代金請求権の消滅時効について説明します。
工事代金未払いの場合に取るべき対処法
工事代金は人件費や資材費などが含まれているため費用が高額になりがちです。
そのため工事代金を払ってもらえないと、自社は資金繰りが悪化して、経営難や倒産のリスクが生じることになります。
したがって、工事代金未払いが発生した場合には、早急に然るべき措置を講じることが必要です。
そこで以下からは、工事代金未払いの場合にまず取るべき対処法を解説していきます。
工事代金未払いの理由を把握する
まずは、工事代金未払いがなぜ起きているのかを把握しましょう。
相手に直接確認する方法もとるべきです。
しかしながら、相手の言い分をそのまま信じるわけにはいかない場合もあります。
相手の言い分だけを信じて判断するのではなく、きちんと調査して、正確な理由を把握しましょう。
予測されうる「工事代金が未払いとなる理由」は、主に以下の4つです。
- 発注者の資金繰りが悪化して支払う余裕がない
- 発注者と元請業者との間で、請負代金の未払いが発生している
- 工事やリフォームなどの内容・仕上がりに発注者が納得していない
- 追加工事の代金にトラブルがある
特に、3と4のケースで未払いが発生しており、かつ契約書もない場合は解決が困難になる可能性が高まります。
それは、リフォームや追加工事の必要性・適切性および、本来支払われるべき工事代金などを立証するのが難しくなるためです。また、実際は資金繰りが悪化して払えないでいるにもかかわらず、相手方は無理やり理由を仕立て上げ、クレームをつけるといった形で未払いという態度を示すケースも考えられます。
こういった場合は、発注者の経済状況を正確に調査して、把握しなければなりません。
発注者の経済状況を正確に調査するには、探偵事務所に相談するのがおすすめです。
工事代金の支払いがあるまで目的物の引き渡しを拒否する
工事代金の未払いが発生したら、当該料金の支払いがあるまで目的物の引き渡しを拒否する権利が工事受注側に生じます。
権利名称は以下の2つです。
- 商事留置権
- 同時履行の抗弁権
未払いがある場合には、こういった権利を行使することも対処法の一つです。
以下からそれぞれの権利について詳しく解説します。
商事留置権
商事留置権とは、商法第521条に記載されている権利です。
例えば改修工事やリフォームなどで注文者から建物を預かっている時に未払いが発生したら、商事留置権を行使し、工事代金の支払いが行われるまで建物の引き渡しを拒否することが可能となります。
同時履行の抗弁権
同時履行の抗弁権は、民法533条に記載されている権利です。
例えば新築の建物の工事代金について未払いが発生した時は、建物の引き渡しをする前であれば、同時履行の抗弁権を行使して、工事代金が支払われるまで建物の引き渡しを拒否することができます。
立替払い制度を利用する(元請業者が特定建設業社の場合)
下請業者が元請業者から工事代金を支払ってもらえず、従業員に給料を払えない場合、建設業法41条2項に基づき、「立替払い」という制度を使うことができます。
本来なら、相手方と直接の契約関係になければ代金は請求できません。
しかしながら立替払い制度を用いれば、直接契約関係のない元請業者から支払いを受けられる可能性があるのです。
もし元請業者が立替払いに応じない場合は、国土交通大臣または都道府県知事に対して立替払いの勧告を求め、大臣や知事からの指導を期待することもできます。
ただし、立替払いの対象となるのは、元請業者が「特定建設業者」の場合のみです。
特定建設業者の定義は以下です。
特定建設業者:「発注者から請け負った工事の全部または一部につき、工事代金4,000万円以上(建築工事は6,000万円以上)となる下請け契約を締結でき」」という許可を受けた業者
特定建設業者が大臣や知事から勧告や指導を受けた場合、それに従わないと業務停止処分を受けることもあるため、勧告・指導が実現した場合、立替払いに応じてくれる可能性は高まります。
ただし、実際に立替払いの勧告が出されるかどうかは、大臣や知事の裁量・判断に委ねられます。
そのため、必ずこの手段を利用できるとは限らないことが注意点です。
工事請負契約を債務不履行として解除する
工事請負契約で決められた工事代金が未払いである場合、「発注者の債務不履行である」と言い換えることができます。
この場合、民法541条にのっとり、請負業者は発注者に対して勧告を出すことができます。
さらに相当期間が経てば、工事請負契約を解除することができます。
また発注者が全ての債務について履行不可能である場合や、工事代金の支払いを拒絶する意思を明確に示した場合などは、民法542条にのっとり、工事請負契約を無勧告解除することも可能です。
工事請負契約を解除した場合、請負業者は工事を継続する義務がなくなります。
なお、すでに実施された工事により発注者が利益を受ける場合には、工事の施工側が民法634条にのっとり、その利益に応じた報酬を請求することも可能です。
この時、発注者が報酬を払わなければ、商事留置権に基づき、目的物を引き渡さないことができます。
不動産先取特権を利用する
不動産の保存・工事・売買に関する取引をした場合、その債権は「不動産先取特権」という権利の対象になります。
この不動産先取特権を使えば、工事をした建物(不動産)を競売にかけて、そこから工事代金を回収することができます。
契約書がなくても、この不動産先取特権を使うことは可能です。
ただし、不動産先取特権を使うには、工事を始める前に、工事代金の予算額を登記しておく必要があります。
契約書がなくても、工事代金請求権を立証する方法
契約書がなくても、法的には工事請負契約は成立するため、未払いの工事代金を回収できる可能性はあります。
契約とは、当事者の間で権利と義務を発生させる「法律上の合意」のことです。
建設工事の請負契約については、契約を締結する際に所定の事項を記載した文書を作成し、相互に交付することが、建設業法19条で義務付けられています。
しかし、これはあくまでも「建設業法上の義務にとどまる」と解釈されており、契約の成立要件ではありません。
したがって、法律上はメールや口約束などであっても、発注者と請負人の合意が事実として存在するのでれば、工事請負契約は成立することになります。
契約が成立したら、その当事者は内容に従って権利・義務を負います。
そのため、発注者は工事代金の支払い義務を負うのです。
つまり工事請負契約の成立を立証できれば、請負人は契約内容に従い、発注者に対して工事代金の支払いを請求できるのです。
ただし、工事請負契約書または工事変更契約書がない場合、工事代金請求権の立証は困難になります。
工事請負契約の成立や請負代金額に関する立証責任は、工事代金を請求する請負人の側にあるため、工事代金請求権を立証しなければ、債権を回収できないことになります。
工事代金請求権が立証できない場合は、以下2つの方法をとることが考えられます。
- 資料や記録を総合的に活用する
- 商法に基づく報酬請求権を主張する
契約書がないのであれば、まずこれらの方法を選択することを検討しましょう。
それぞれの方法について、以下から詳しく解説します。
資料や記録を総合的に活用する
契約書がない場合は、それ以外の間接的な証拠を積み上げて、工事代金請求権を立証するしかありません。
工事代金請求権の立証に役立つ証拠として、以下が挙げられます。
- 発注者とのメールやメッセージのやり取り
- 発注者との打ち合わせ資料やメモなど
- 発注者との電話の録音
発注者が工事内容や代金発生について同意していた事実が、証拠内に表れていれば、工事代金請求権を立証できる可能性があります。
こういった証拠集めには、探偵の力を借りることも有効です。
探偵であれば、全てのメールやメッセージから証拠能力が高いものについて洗い出してくれたり、電話の録音機器を貸してくれたり、資料をまとめてくれたりと、あらゆる観点から力になってくれることでしょう。
商法に基づく報酬請求権を主張する
もし、工事請負契約に基づく工事代金請求権を立証できない場合でも、商法上の報酬請求ができる場合があります。
商法第512条では、「商人(会社・事業者)がその営業の範囲内で、他人のために何らかの行為をした時には、相当な報酬を請求できる」ことが認められています。
したがって、請負業者が発注者のために工事を実施した場合、それが契約(合意)に基づかなかったとしても、発注者に対して実施内容相当の報酬を請求することが可能となるのです。
ただしこの場合の報酬における具体的な金額は、契約で明確に決められるような工事代金とは異なり、実施された工事の内容に応じて判断されることになります。
未払いの工事代金を回収する方法
工事代金の支払いは、相手から支払ってくれるのを待つだけではいつまで経っても受け取れない恐れがあります。
したがって相手からの支払いが遅れている場合には、以下5段階の手順に基づいて回収を目指しましょう。
- 電話や訪問などをして工事代金についての催促・交渉をする
- 弁護士から内容証明郵便を送る
- 支払い督促を申し立てる
- 仮差押えをしてから、民事訴訟を提起する
- 強制執行(差し押さえ)を行う
できる限り裁判まで発展する前に解決したいものです。
しかしながら、3まで到達しても未払い代金が回収できない場合、最終的には裁判に至ることになります。
以下からは、各手順について細かく解説します。
1.電話や訪問などをして催促・交渉する
未払い工事代金の回収をしたい場合、まずは相手方の担当者などに連絡を取り、支払いを催促します。
例えば単なる事務手続き上のミスや、契約内容についての認識違いが起きていただけなのであれば、改めて支払い手続きの確認をすることで、すぐに回収できるでしょう。
一方で、相手方が資金難や経営難などで支払いが遅れている、もしくは支払い不能の場合は、返済計画について改めて交渉する必要があります。
交渉においては、可能な範囲で支払期限を延期したり、現時点で支払えるだけ支払ってもらい、後は分割払いで回収したりするなどの対応をせざるを得ない場合も想定されます。
相手方に保証人がいる場合には、保証人に対する責任追及も検討すべきです。
工事代金の未払いがあっても、こうした交渉の手段であれば手間や時間、費用の負担を軽減できる可能性が高く、最も望ましい方法といえるでしょう。
しかし、相手方が催促に応じない場合は、繰り返し催促する必要があります。
催促は電話以外にも「催告書」という形でメールや書面のような記録が残る方法でも行いましょう。
催告書には、支払期限と金額、遅延損害金が発生することなどを明記します。
遅延損害金は、法定利率の年3%よりも少し高めに設定しておくといいでしょう。
直接訪問して催促を行う場合にも、この催告書を持参しましょう。
深夜・早朝の訪問や、脅迫的な口調での催促は、ルール違反です。
しかしながら、法的な許容範囲内で粘り強く催促することで、相手に心理的なプレッシャーをかけ、支払いに応じるよう促すのは交渉のひとつのテクニックです。
こういった場合、催告書や訪問日時などの記録は、逐一取っておくことが重要です。
万が一、後で裁判になった時に証拠になるからです。
2.弁護士から内容証明郵便を送る
繰り返し催促しても相手が未払い工事代金の支払いに応じない場合は、弁護士に依頼し、弁護士名義で内容証明郵便を送付することで支払いを求めます。
内容証明郵便とは、差出人と宛先、差出日時、内容を郵便局が証明するサービスです。
請求内容を明確化することができる上に、民法150条1項に基づく、工事代金請求権の消滅時効の完成を半年猶予する効果もあります。
同時に配達証明も併用すれば、督促を行った事実を記録として残すことができ、「書類を受け取っていない」などと反論される可能性を潰すことが可能です。
内容証明郵便には、以下の点を明記しましょう。
- 日付
- 相手方の社名・代表取締役社名・住所
- こちら側の社名・代表取締役名・住所
- 催促する未払い工事代金の金額
- 支払期限
- 支払先の振込口座
- 期限までに支払いがなければ、訴訟等の法的手段をとるといった説明
※訴訟の際は債権金額だけでなく遅延損害金や弁護士費用も請求金額に加えること
内容証明郵便に記載する支払期限は、「内容証明郵便を受領後7日以内」など、タイトな期限を設定することを推奨します。
この理由は、内容証明郵便を送る時点で、既に本来の支払い期限を過ぎていることが多いためです。
このように弁護士から内容証明郵便を送ることで、「支払わなければ法的手段を取る」というこちらの本気度合いを伝えることができます。
債権者側の本気度合いは、相手へのプレッシャーをさらに強め、支払いを促しやすくなります。
3.支払い督促を申し立てる
支払督促とは、裁判所に申し立てて督促状を相手方に送ってもらう手続きのことです。
支払督促を行う手順は、支払督促申立書などの必要書類を揃えて、簡易裁判所に申し立て、裁判所から支払督促を発布してもらうという形になります。
支払督促のメリットは、訴訟などの法的手段に比べて手続きが比較的容易であることと、手数料が安く、費用が訴訟の約半額で済むということです。
また支払督促について2週間以内に相手が異議を申し立てず、代金の支払いにも応じなければ、督促に裁判の判決と同じ効力を有する仮執行宣言を付すことができます。
仮執行宣言が付されると、相手が支払いに応じない場合は強制執行を申し立てられるようになります。
ただし、相手が異議を申し立てた場合は、通常の訴訟手続きに移行してしまうことには注意が必要です。
訴訟には、手間や費用がかかる金銭的リスクがあります。
4.仮差押えをしてから、民事訴訟を提起する
支払督促をしても未払い工事代金の回収に至らない時は、裁判を起こすことになります。
裁判において重要なのは、「裁判の前に仮差押えをする」ということです。
仮差押えとは、訴訟の前に発注者の財産を凍結し、処分できなくする手続きです。
仮差押えをしておかないと、もし裁判に勝訴しても相手側から代金を回収できないリスクがあります。
例えば、裁判中に相手が銀行預金を使い切ってしまったり、所有していた不動産を売ってしまったりして、勝訴しても代金を回収できないというリスクを、裁判の前に仮差押えをしておくことによって回避することができるのです。
仮差押えをしたら、いよいよ訴訟を提起します。
この場合は、民事訴訟であり、裁判所の公開法廷で行われる法的手続きです。
管轄する裁判所は、訴額によって異なります。
訴額が140万円未満であれば簡易裁判所、140万円以上であれば地方裁判所となります。
また、訴額が60万円以下の場合は、「少額訴訟」という方法もとられがちです。。
訴訟の起こし方は、訴状を作成し、工事代金請求権が発生していることを証明できる証拠を集めて、裁判所へ提出するといった形になります。
契約書がなくても、工事代金請求権を立証できれば訴訟は提起できます。
また、相手方が裁判に出頭しなかったり、答弁書を提出しなかったりした場合は、訴状に書いた主張をすべて認める判決が言い渡されるでしょう。
しかし、相手方が反論の答弁書を提出するなど争ってきた場合は、双方が主張と証拠を出し合い、その主張を的確に証明できた側が確定判決を得られ、勝訴することになります。
ただし、実際には和解に至ることも多いものです。
和解が起きた場合、和解調書を得ることになります。
確定判決や和解調書を獲得できれば、次の段階である「強制執行」を行うことが可能です。
⑤強制執行(差し押さえ)を行う
強制執行とは、相手方が債務不履行の場合、裁判所を介して差し押さえなどの手続きを行うことにより債権を回収する手段です。
強制執行を申し立てるには、「債務名義」が必要となります。
債務名義とは以下を指します。
- 確定判決
- 仮執行宣言付判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 公正証書(執行証書)
- 和解調書
強制執行の方法としては、主に以下の3つがあります。
- 債権執行(預金の差し押さえなど)
- 不動産の競売
- 動産執行
以下からそれぞれについて詳しく解説します。
債権執行(預金の差し押さえなど)
強制執行により預金を差し押さえた場合、発注者の預金先の金融機関から、直接自社に対して工事代金の支払いを受けることが可能です。
不動産の競売
不動産を差し押さえた場合は、相手方が所有している不動産を判決に基づいて競売にかけることになります。
競売により不動産を売却できたら、その代金から債権を回収できます。
動産執行
動産執行とは、相手が所有している現金を差し押さえて、工事代金の支払いを受けることです。
しかし、通常は動産執行で得られる金額はあまり多くありません。
日頃から多額の現金を手元に置いている人は少ないからです。
動産執行という手段では、発注者に対して強力なプレッシャーをかけることになります。
そしてその効果により後日、工事代金の全額を回収しやすくすることが真の目的です。
工事代金請求権の消滅時効に注意
工事代金請求権には、消滅時効があります。
これを過ぎると、工事代金を回収することができません。
したがって、相手方の代金支払いが遅滞している場合には、消滅時効が過ぎる前に手を打つことが重要です。
消滅時効期間と起算点
2020年4月以降の民法(166条)においては、消滅時効期間は、工事代金は支払期限から数えて5年です。
ただし、2020年3月以前に発生した工事代金は、旧民法が適用され、消滅時効は3年となります。
時効の起算点は、基本的には支払期限となっていますが、起算点が明確でない場合には、工事完成日(引き渡し時)や工事請負代金請求権の発生時となることが多くなります。
つまり、契約書がない場合の時効起算点は、工事請負代金請求権を立証できた時です。◉-2、消滅時効の進行を阻止する方法
消滅時効に関して、「時効更新措置」(旧民法では「時効中断措置」)という、時効の時期を変動させる手段があります。
時効更新措置として、以下があります。
- 催告(民法第150条第1項)
- 裁判上の請求等(民法第147条)
- 仮差押え等(民法第149条)
- 債務承認(民法第152条第1項)
- 強制執行、担保権の実行、競売等
それぞれ、時効の完成猶予、更新、ストップ、リセットなどに関わります。
催告(民法第150条第1項)
裁判所を介さずに、弁護士から内容証明郵便で代金を請求した場合、時効の進行が6ヶ月ストップします。
裁判上の請求等(民法第147条)
支払督促、訴訟、調停、和解など、裁判上の請求等を行うと、その手続きが終了するまで、時効の完成は猶予されます。
請求が認められれば、時効期間が10年更新されます(民法第169条第1項)。
仮差押え等(民法第149条)
仮差押え・仮処分を行った場合、その事由が終了した時点から6ヶ月間、時効の完成を猶予することができます。
債務承認(民法第152条第1項)
債務承認とは、債務者が未払い金の存在を認める行為を指します。
以下のような行為があった場合、それまでの時効進行がリセットされ、時効期間が再スタートします。
- 工事代金の一部支払い
- 工事代金の支払いを約束する書類の作成
- 工事代金の減額・支払い期限の延長などの嘆願
強制執行、担保権の実行、競売等
強制執行、担保権の実行、競売等が行われた場合、消滅時効の一時的な完成猶予、或いはリセットがなされます。
契約書のない未払い工事代金の債権回収は、早急に探偵や弁護士に相談を!
今回は、未払いの工事代金についての対処法や回収方法、消滅時効について解説しました。
契約書がない工事において発生してしまった未払いの工事代金の債権回収を進めるにあたっては、まず工事代金請求権を立証することが重要であるといえます。
工事代金請求権を立証するには、工事内容と工事代金の合意についての証拠を集めることが必要となります。
証拠集めで大きな力になってくれるのが、探偵です。
探偵を選ぶ際のポイントは、債権回収についての実務経験があり、なおかつその後必要な存在となる弁護士と連携しているかどうか、などです。
工事代金請求権の消滅時効は意外に短いため、未払いの工事代金がある場合には、早急に手続きや専門家への相談をすることをおすすめします。
債権回収に関する資産・財産調査はSAT探偵事務所にお任せ!
債権回収で重要なのが、相手側に返せるだけの資産があるかどうか、です。
まずはそこを調査によって明確にした上で、債権回収を弁護士や債権回収業者(サービサー)に依頼するのが確実です。
SAT探偵事務所には、警察OBの探偵が在籍しており、単なる資産調査だけではなく、意図的に債務者側が隠した財産などもくまなく調査が可能。
また、工事代金の未払いのようなケースは、意図的に債権を隠す債務者も多くみられるため、未払いの工事代金などが発生した場合、早急な調査を行うことが何より大切です。
「相手側から払う気配が全く感じられない」など、回収リスクを感じた段階で、メールやお電話にて、早急にご相談ください。
警察OBに直接相談できる探偵事務所
受付時間/10:00~20:00
※LINE相談は友達登録をして送られてくるメッセージに返信することで行えます。