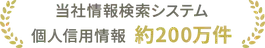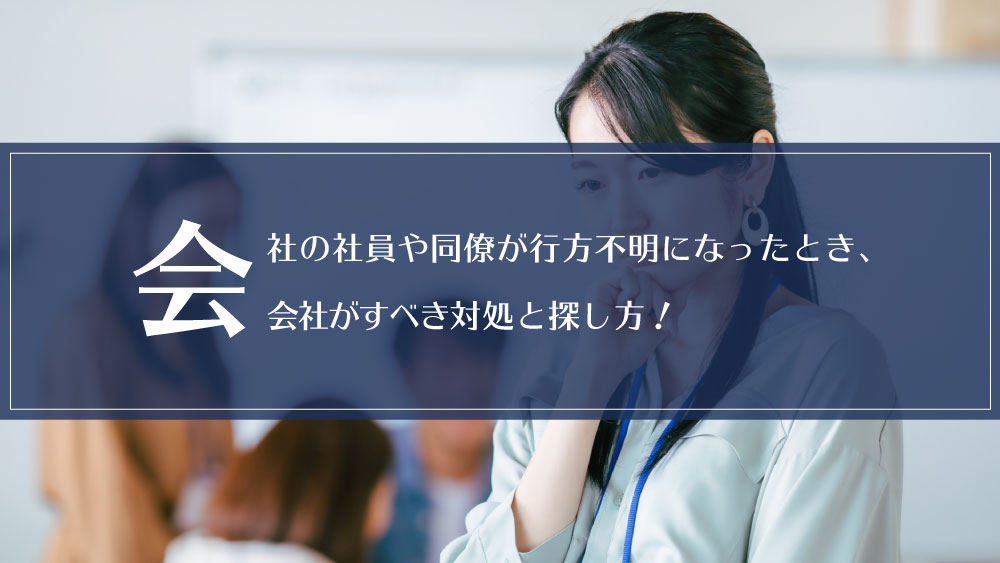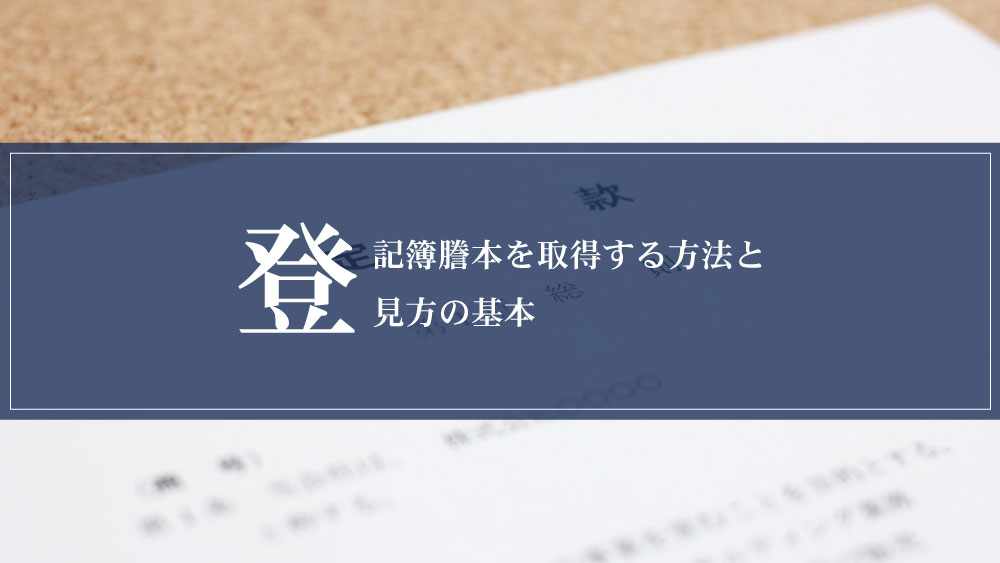サッと読める!
ためになるSATコラム
カテゴリーで絞り込み
個人向け調査
既存不適格建築物とは?違反建築物との違いも交えて解説
【投稿日】2022年9月17日

「既存不適格建築物」という言葉を聞いたことがありますか?
不動産関係の方以外は、あまり聞き馴染みのない言葉だと思います。
これは、実は法律用語ではない(法律には書いていない)のですが、法律用語に準ずるものとして、一般的に使われています。
そして、現存する建築物の中で、この「既存不適格建築物」に該当するものは、かなり多いのが現状です。
それでは、いったい既存不適格建築物とはどんなものでしょうか。
本記事では、既存不適格建築物とは何か、というところから、既存不適格建築物の「不適格」になりやすい規定、既存不適格建築物が発生する理由、既存不適格建築物の規制緩和と解除について、また、既存不適格建築物のデメリットと、建て替えや売却時の注意点について、詳しく解説していきます。
既存不適格建築物とは
既存不適格建築物とは、既に建っている建築物のうち、建築・完成時は「旧法・旧規定の基準で合法的に建てられた建築物」であったが、その後、法令の改正や都市計画変更などにより、現時点で適用される法律においては適合しない部分が生じてしまっている建築物のことを言います。
建築基準法3条第2項では、建築基準法及び施行令等が施行された時点において、既に存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、建築基準法及び施行令等の規定に適合しない部分を持っていたとしても、これを違反建築物としないという特例が設けられています。
既存の適法な建築物が法令の改正等により違反建築物とならないよう、新たな規定の施行時、または都市計画変更等による新たな規定の適用時に、現存するもしくは工事中の建築物については、新たに施行・適用された規定に適合していないものには適用を除外することとしているのです。
また、原則として、増改築等を実施する機会には、当該規定に適合させることとしています。
この規定により、事実上違法な状態であっても、法律的には違法でない建築物のことを「既存不適格建築物」と呼んでいます。
建築基準法第3条第2項
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
既存不適格建築物の「不適格」になりやすい規定
では、既に建っている建築物のどこが、法令や規定に適合せず、既存不適格建築物になりやすいのでしょうか。
ここでは、建築物が「不適格」になりやすい規定を挙げていきます。
建築物が不適格になりやすい規定は、次の8つです。
- 建ぺい率・容積率
- 前面道路の幅員による制限
- 道路斜線制限
- 隣地斜線制限
- 北側斜線制限
- 日影規制
- 耐震基準
- 防火地域・準防火地域
一つひとつ、どのような規定かを見ていきましょう。
①建ぺい率・容積率
建ぺい率とは、敷地面積に対する建物面積(建物を真上から見た時の面積)の割合を言います。
建物を建てる土地に、どのくらいの広さの建物を建てられるかの数値が建ぺい率です。
一方、容積率とは、敷地面積に対する延床面積の割合を指します。
延床面積とは、建物の全ての階の床面積を合計した面積のことです。
建ぺい率や容積率の数値が高いほど、敷地に対して建物の面積は大きくなります。
しかし、日当たりや風通し、防災の面で制限する必要があるため、建築基準法によって用途地域や防災地域等の種別ごとに、それぞれの上限が定められているのです。
この上限が、法改正や規定の施行等により変わることがあり、知らないうちに建ぺい率や容積率の制限をオーバーしていた、ということがあります。
②前面道路の幅員による制限
建築基準法の前身にあたる市街地建築物法(大正8年施行)では、約2.7m以上の道に面していることが最低条件とされていました。
しかし、1938年に法改正され、現行の建築基準法では、原則として建物の敷地は幅員4m以上の道路に接している必要があり、その要件を満たさないと建築は認められないということになっています。(接道義務)
しかし、古くからある既成市街地では、4m未満の道が多いため、沿道の建物のほとんどが、既存不適格建築物となり、建て替え不可となってしまうのです。
こうした道路に面した敷地に建築を行う場合は、原則としてその中心線から2m後退しなければならないとされています。
例えば、幅2.7mの道の沿道に立ち並んでいる建築物を建て替える際には、敷地境から0.65m後退しなければなりません。
③道路斜線制限
道路斜線制限とは、道路の日照や採光、通風に支障をきたさないように、また周辺に圧迫感を与えないように、建築物の高さを規制したルールのことです。
前面道路の反対側の境界線から、一定の勾配で記された線(道路斜線)の範囲内に、建築物を建てなければなりません。
道路斜線は、用途地域や容積率、道路の幅員などで適用距離と適用角度が変わり、建物の高さと位置が決まります。
これが、用途地域や、先に述べた容積率の上限、前面道路の幅員制限などの法改正や規定の施行により、道路斜線制限も変わり、既存不適格建築物になってしまう場合があります。
④隣地斜線制限
隣地斜線制限とは、隣人の日照や採光、通風等、良好な環境を保つために、建築物の高さを規制したルールです。
隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(隣地斜線)の範囲内で建物を建てることになっています。
この一定の高さと勾配は、用途地域によって異なるため、用途地域の規定が変わることにより、既存不適格建築物になってしまうことがあります。
⑤北側斜線制限
北側斜線制限とは、北側隣地の日照の悪化を防ぐことを目的としたルールです。
北側斜線制限は、北側隣地境界線を起点として、「高さ」と「斜線の勾配(角度)」によって規制されます。
しかし、建築基準法が定めている北側斜線制限が全国共通の規定であるのに対し、「高度地区」と呼ばれる地域では、都市計画法が定める法規により、制限の内容が自治体ごとに異なります。
この都市計画法は、昭和43年に制定され、最終改正は平成18年であるため、これ以前に建てられた建築物の中には、既存不適格建築物となってしまうものもあるのです。
⑥日影規制
日影規制とは、「日影による中高層の建築物の制限」の略で、冬至の日を基準にして、一定時間以上の日影が生じないよう、建物の高さを制限するものです。
1970年代に入って、マンションなどの高層建築が次々に建築されるようになり、日照阻害の問題がクローズアップされ、日照権の訴訟が多発したため、1976年に建築基準法改正で導入されました。
したがって、この法改正以前に建てられた建築物の中には、既存不適格建築物にあたるものも多くあります。
⑦耐震基準
耐震基準は、1971年と1981年、2000年に大きな改正が行われました。
これにより、1981年の建築基準法の改正によって、1981年5月31日までに確認申請を受けた建物は「旧耐震」、1981年6月1日以降の確認申請を受けた建物は「新耐震」と呼ばれます。
旧耐震では、「震度5程度の中規模の地震で大きな損傷を受けないこと」が基準となっていました。
これに対して、新耐震では、「中地震では軽微なひび割れ程度の損傷にとどめ、震度6程度の大規模な地震で建物の倒壊や損傷を受けないこと」という基準に変わっています。
2000年の改正は、木造住宅に関するもので、基礎は地耐力に合ったものと規定され、木造住宅でも事実上地盤調査が義務付けられています。
また、柱や筋交いを固定する接合部の金物が指定されて、耐力壁の配置のバランスも規定されました。
したがって、2000年以前に建てられた木造住宅、1981年以前に建てられた建築物の多くが、現行の建築基準法のもとでは、既存不適格建築物にあたります。
⑧防火地域・準防火地域
防火地域・準防火地域とは、都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として指定されるエリアのことです。
火災の危険を防いで取り除くため、多くの場合、駅前や建物の密集地、幹線道路沿いなどが指定されています。
しかし、東京都では、木造住宅が密集して道も狭い地域が多く、防火地域・準防火地域だけでは対応しきれないため、2003年に「東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制」が定められました。
このエリアでは、耐火構造や延焼抑制機能を持つ外壁や屋根などを使用しなければなりません。
大阪市でも、同じような条例が定められており、これに反する建築物は、既存不適格建築物となります。
既存不適格建築物が発生する理由
建築基準法や都市計画法、自治体の条例や地区計画等の様々な規制は、技術の発展や社会的要請を背景に、時代とともにどんどん変化していきます。
一方で、建物は50年、100年といった期間でも存続するため、ある意味、法律の寿命よりも建物の寿命の方が長いと言えるでしょう。
一つの建物が存続する間に、法律や条例が変わってしまうことが、既存不適格建築物が発生する主な理由となっています。
例えば、今年新築した建物であっても、10年後、20年後には、既存不適格建築物になってしまう可能性は十分に有り得るのです。
既存不適格建築物の規制緩和
既存不適格建築物は、増改築等の際に、建物全体を現行法(着工時の法律)に適合させる必要があります。
しかし、建物の状況によっては、これは簡単なことではありません。
例えば、旧耐震基準で設計された建築物の構造強度を、補強によって現行基準に全て適合させることは、理論上は可能であるとしても、現実には不可能である場合が多いでしょう。
このため、法律上では全く増改築できない建築物が出てくることになります。
こうした問題から、平成17年より既存不適格建築物について、一定の条件下では緩和が行われることとなりました。
それまでは、特定行政庁の運用指針に任せていたのですが、平成17年の法改正時に、その運用指針を明確化する目的で、国土交通省が統一基準である「既存の建築物に対する規制の緩和」というタイトルで、建築基準法86条の7が制定されます。
これにより、一定の規模以下で増改築を行う場合には、既存部分に遡及しないことが定められました。
既存不適格建築物の解除
既存不適格建築物は、法の不遡及の原則と、法改正の度に建っている建築物を全て違反とすることで起きる社会的混乱を防ぐための制度であり、現行法に適合しない状態を、半永久的に続けることを認めているわけではありません。
このため、建築基準法には、既存不適格が解除される条件が規定されています。
一度解除されると、その建物や敷地は全て解除された時点の法律に適合させなければならず、時には増改築や改修、補強などを必要とされます。
例えば、一定規模以上の増改築や改修が行われた建物と、その建物が立っている敷地は、敷地及びその棟全体を現行法に適合するよう改修や補強をすることが必要です。
また、上記にあたらない改修などによって、一度現行法に適合した部分は、既存不適格が解除されているので、着工時の状態に戻すことは、違反となります。
法規制の緩和によって、現行法に適合するようになった部分も、解除されます。
違反建築物との違い
ここまで、既存不適格建築物について述べてきましたが、既存不適格であっても決して何か違反しているという訳ではありません。違反建築物とはまた別物です。
違反建築物とは
既存不適格建築物に対し、違反建築物とは、建築当初から建築基準法や条例などの法令に適合していない建築物、または法令に適合しない増改築工事や用途変更を行った建築物などを言います。
したがって、法令に適合しない状態の建築物が全て既存不適格建築物になるわけではなく、建設や増改築時点で建築基準法や条例など法令に違反していた建物が、違反建築物として扱われるのです。
例えば、新築時は建ぺい率・容積率ともに既定の範囲内であったが、無許可または許可内容と違う増改築を繰り返した結果、規定をオーバーしてしまったというケースがあります。
また、確認申請時に提出した図面と、実際に建築した建物の構造や仕様が異なっている場合や、確認申請時と違う用途で使用しているなどの場合も、違反建築物にあたります。
違反建築物の是正命令
違反建築物には、強制的な是正命令が下されます。
建築基準法第9条には、違反建築物に対する措置が明記されており、特定行政庁は、工事途中でも工事を停止させることや、既に完成している場合でも、違反建築物の除去や移転・改築・使用禁止などの措置を命令することが可能です。
また、違反建築物の設計者や工事業者には、宅地建物取引業法による免許の取消や業務停止命令などの処分が与えられる場合もあります。
さらに、平成19年の改正建築基準法により、罰則が強化されており、例えば、工事施行停止命令違反による懲役刑が1年から3年に延びたり、建築確認や検査による罰金が30万円から100万円に引き上げられたりしています。
既存不適格建築物のデメリット
既存不適格建築物は、違反建築物とは違い、合法ではありますが、今の法令の基準を満たしているわけではないため、デメリットが存在します。
それは、以下の2つです。
- デメリット1:同じ建物を建て替えることができない
- デメリット2:銀行の担保評価が低い傾向がある
それぞれ見ていきましょう。
デメリットその1:同じ建物を建て替えることができない
既存不適格建築物の最大のデメリットは、「同じ建物を建て替えることができない」ということです。
今の法令基準を満たしていないため、建て替えで新築しようとすると、今の法令に適合させる必要があり、現在の既存不適格建築物と同じ建物は建てられないことになります。
今の法令に適合させるために、建物規模が小さくなってしまったり、形状が変わってしまったりすることもあるでしょう。
また、昔の仕様のままであれば、建築コストも安く済んだところを、今の法令の基準に合わせようとすると、建築コストまで高くなることもあります。
既存不適格建築物は、建て替えの際に、所有者が予想していなかった不利益を受けてしまうという点がデメリットと言えるでしょう。
デメリットその2:銀行の担保評価が低い傾向がある
もう一つのデメリットは、銀行など金融機関の担保評価が低い傾向があるということです。
既存不適格建築物に対する評価は、金融機関によって異なりますが、総じて担保評価が低く評価され、融資を受けにくいといった問題があります。
古い建築物は、近い将来建て替えの可能性もありますが、同様の建物が建て替えられない可能性が高いことから、金融機関は融資にあたって一定のリスクがあると判断しているのです。
また、旧耐震基準の建物は、大きな地震が発生した時に倒壊の危険性が高いため、資産価値が下落します。
旧耐震基準の建物では、住宅ローン控除が利用できないという不利益もあり、住宅ローン控除が利用できる物件にするためには耐震補強等のリフォームが必要で、多くのコストがかかることから、資産価値が低くなってしまうのです。
建て替えや売却時の注意点
既存不適格建築物は、建て替えでは現在と同じ仕様の建物が建てられないということが、一番の注意点です。
ただし、建築基準法の規制は、必ずしも強化の方向性だけでなく、緩和の方向性もあります。
建て替えた方が改善される場合もあるため、建て替えを行う際には、しっかりと建築プランを検討してから判断するといいでしょう。
また、売却に関しては、既存不適格建築物であることで、価値が下がっている場合と、上がっている場合があります。
先に述べたように、旧耐震基準のような既存不適格であれば、価値は低くなっていますが、容積率が指定される前に建てられたような、今の容積率では建てられない規模の広い延床面積を持つ建物であれば、価値は高くなる傾向にあります。
売却の際は、査定等でしっかりと価格を調べ、価格の理由に納得した上で売却するといいでしょう。
既存不適格建築物は合法だが半永久的にではない
本記事では、既存不適格建築物とは何かというところから、違反建築物との違い、既存不適格建築物のデメリット、建て替えや売却時の注意点を解説してきました。
既存不適格建築物は、現行法には適合しないものの、法律的に合法ではありますが、それは、半永久的に保障されたものではないということは、覚えておいた方がいいでしょう。
建物は、どんなものもいずれ老朽化します。
そうした場合に、建て替えるか、売却するか、壊して更地にするかなど、判断を迫られることになるでしょう。
自宅や自社物件が既存不適格建築物である場合は、将来のことを考えて、今からどうするかを検討しておくことをおすすめします。
既存不適格建築物かどうかは、中古不動産購入の際には特に注意しよう!
既存不適格建築物を自分で保有している場合であれば、建て替えや売却の際に注意すれば良いですが、特に注意すべきなのが、中古不動産を購入する場合です。
「少し古いけど、安いし、ちょっとしたら建て替えればいいか!」と購入してしまって、購入後に、既存不適格建築物だったと分かるという事もあります。
そのため、中古不動産を購入する際には、しっかりとその不動産の実態について、または、不動産の売主についてしっかりと調べておく必要があります。
探偵事務所SATでは、こういった不動産の実態調査や、売主の素性や経歴、過去に犯罪歴がないかなどの信用調査、反社会的勢力との繋がりがないかどうかの調査を承っております。
購入してからでは遅いので、もし、中古不動産購入の際に、「なんとなく売主の素性が知れない」という場合には、探偵事務所SATにご相談ください。
警察OBに直接相談できる探偵事務所
受付時間/10:00~20:00
※LINE相談は友達登録をして送られてくるメッセージに返信することで行えます。